日外会誌. 125(4): 359-364, 2024
会員のための企画
外科専門医・小児外科専門医取得のための外科医の教育体制と外科教育研究―日米における比較
|
1) 鹿児島大学 学術研究院小児外科学分野 家入 里志1) , 宮田 真2) , 村上 雅一1) , 倉島 庸3) |
わが国と米国(北米)における外科専門医・小児外科専門医の教育および外科教育研究を比較した.国内外科専門医は筆記試験と手術経験症例数,学術活動を必要とし,米国の外科専門医も筆記試験と手術経験症例数を必要とする点では同じだが,米国の要件は本邦よりはるかに厳しく,専門医取得時点で自立した外科医としての能力が求められる.小児外科専門医も米国小児外科専門医は国内小児外科専門医に比較して約10倍近い執刀経験を必要とし,同様に独立した小児外科医としての技量とフェローの指導能力を求められる.外科教育研究は北米で先行し,外科教育においてプログラムやカリキュラム構築に貢献している.国内でも日本外科教育学会が発足し,今後の外科医教育と外科教育研究の発展が期待される.
キーワード
外科専門医, 小児外科専門医, 外科教育, 外科教育研究, 日米比較
I.はじめに
国内で2018年に新専門医制度が発足し,新制度による外科専門医が2021年に誕生している.これまで学会主導により専門医の育成とその認定が担われてきたが,今後は主として専門医認定を日本専門医機構が行うこととなり,さらに認定はサブスペシャルティ領域にも拡大される予定である1).しかし専門医育成のプログラム・カリキュラムそのものは日本外科学会やサブスペシャルティ学会がその承認を行っており,外科専門医およびサブスペシャルティ専門医に関しても,教育と育成は実質的に学会が担っている状況である.
今回外科医の教育という視点で,外科専門医と小児外科専門医における本邦と米国のシステムを対比解説し,北米ですでに研究領域として確立している外科教育研究にも触れる.
II.本邦における外科専門医・小児外科専門医の取得条件とその教育体制(村上 雅一)
本邦の外科専攻医は3年間のプログラムに所属し,基幹施設もしくは連携施設においてトレーニングを行う.外科専門医取得に必要な主な要件としては,筆記試験合格と手術経験症例数,学術活動となる2).
手術経験は,表1に示すように350例(うち術者120例)を必要とし,さらに各領域の最低症例数が,消化管および腹部臓器が50例以上,ほか乳腺,呼吸器,心臓・大血管,末梢血管,頭頚部・体表・内分泌外科,小児外科がそれぞれ最低10例以上と規定され,内視鏡手術を10例以上含むことも要件とされる.また外傷についても従来10例以上の経験を求められたが,現在は外傷に関する講習会や研修コースを受講することで,代替可能である.必要手術経験に関しては,National Clinical Database (NCD)登録を基に算出され,現時点で内容や手技の評価は行われない2).
学術活動は単位制となっており,20単位以上を必要とする.学会での研究発表や論文発表が対象で,学会の規模や雑誌によって単位数が異なる.学会発表は日本外科学会定期学術集会での発表は1回20単位となり,論文発表は日本外科学会雑誌や英文誌は1編20単位と規定されている2).
小児外科専門医取得には外科医として7年以上の経験を有することと,日本小児外科学会が認定する施設において,36カ月以上の研修を行うことが求められる3).小児外科専門医取得に必要な手術経験は,①小児外科手術150例以上,②新生児20例以上(うち少なくとも5例は執刀とし,残りは助手でも可),③5歳以下乳幼児100例以上,④鼠径ヘルニア類以外50例以上となっている.手術指導は各施設に完全に委ねられており,外科専門医と同様にNCD登録を基にカウントされ,術式の内容や手技の評価は行われない3).
学術活動は単位制で30単位以上を必要とするほか,小児外科に関する筆頭論文1編以上と日本小児外科学会が主催する年2回の学術集会に1回以上の参加が求められている3).
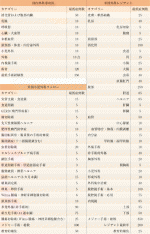
III.米国における外科専門医・小児外科専門医の取得条件とその教育体制(宮田 真)
米国で外科専門医を取得するには,まず米国卒後医学教育認定評議会(ACGME)に認可されたレジデンシープログラムで5~7年の修練の間,表1に示すような最低限の執刀症例を経験することが必要である.そののちABS (American Board of Surgery)4)によるqualifying exam(筆記試験)でマルチプルチョイスの問題(MCQ)を8時間かけて約300問解く.筆記試験に合格すればcertifying exam(口頭試験)で一般外科・腫瘍・外傷などからなる症例(30分×3セッション)に対するマネージメントを問われ,これに合格することで晴れて「一般外科医」を名乗れることとなる4).
小児外科専門医となるには,上記の一般外科専門医になるために必要なレジデンシー(多くは2年ほどの研究期間を外科レジデンシー3年目以降の時期に挟み,小児外科フェローシップに入るための競争力つまり業績を積む)を経て,アメリカ・カナダにおける40余りのフェローシップポジションを競う.
小児外科フェローシップのポジションを勝ち取ったものは,2年のフェローシップを受け,表1の最低限の執刀症例を経験することとなる.2年間で執刀総数800件は米国のプログラムであればどれも十分達成可能であり,ほとんどのフェローは1,000~1,200件以上を執刀している印象がある.一方,症例のカテゴリーに関しては,新生児手術(75件)や腫瘍切除術(25件)などで症例数を満たすのに苦労する場合も散見する.フェローシップ修了後に一般外科の時と同様にqualifying (5時間で200問のMCQ), certifying exam(30分×5の口頭試験)を受け,それらに合格することで小児外科専門医となる.
ちなみに,小児外科フェローシップを一度目で獲得できなかった場合は,二度・三度と挑戦する「フェローシップ浪人」も稀ではなく,その間小児外科のサブスペシャルティ(外傷・外科集中治療,低侵襲手術,胎児手術,外科イノベーションなど)のフェローシップをすることでさらなる競争力を付けたうえで再挑戦する.
一般外科・小児外科ともに,専門医の更新制度は近年変更され,従来あった10年に一度の200問のMCQ試験から,2年に一度,40問のMCQ試験となった.さらに変更後は,試験はオープンブックとなり,答えを自由に調べることができるようになった.任意の2週間の間に自分のペースで自宅などでも受験可能である.正答率80%で合格となる.
一般外科・小児外科・その他の外科を問わず,日米の専門医制度の違いで特筆すべきは,アメリカでは極めて稀な例外を除き,専門医(board certification)なしで独立して診療が不可能なことである.日本には「足の裏の米粒のように,取っても食えないが取らないと気持ち悪い」という揶揄的表現がある(もっとも,これは専門医ではなく博士号に対して使われるものであるが).米国の医師にとって専門医は「取らないと気持ち悪い」というレベルのものではなく死活問題であり,いわば「目の中の米粒」といったところだろう.
小児外科医としての基礎は成人外科にあり,外科医としてのしっかりとした土台を成人外科で作るのが極めて重要と考える.上記のような一般外科レジデンシー→小児外科フェローの流れもそれを反映した理にかなったものと思われる.一方その過程は長く,現行のシステムではほぼ10年を要する.一般外科と小児外科を統合したレジデンシープログラム(6~7年)の議論もなされており,近い将来に実現する見込みである.
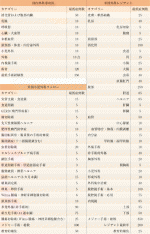
IV.本邦と米国における外科専門医育成と小児外科専門医育成の違いとその特徴
今回経験症例数を対比したが,日本の外科専門医取得と米国ABSのCertificate取得において,最低経験症例数が大きく異なる(350例vs. 850例)ことに加え,さらに大きく異なるのはその執刀症例数であろう.米国外科レジデントは850例が最低の経験症例数だが,これはほぼ執刀数であり,通常1,000例以上の執刀経験を得ていると考えられる.またレジデント最終年の手術症例数と教育補佐が求められるなど,ABSのCertificateを取得した時点で指導能力が求められている.筆記試験合格は共通だが,問題数もかなり多く,さらに日本では行われていない口頭試験が最終試験として設定されているのも特徴である.
小児外科専門医に関してはABSの小児外科Board Certificate取得において求められる経験症例数は本邦の小児外科専門医よりはるかに多く,米国小児外科フェローが2年間で800以上の経験症例をほぼすべて執刀している(実質1,000~1,200例以上)ことを考えると,おそらく本邦小児外科専門医に必要な150例の10倍近い執刀経験を有すると考えられる.また米国小児外科フェローに求められる経験症例も疾患・術式別に細かに規定され,これは国内小児外科指導医に必要な執刀要件を大幅に上回っている.加えて教育的補佐50例もおそらくABSの小児外科Board Certificateは次のフェロー指導が求められているためである.北米では専門医になった瞬間,外科医としての自立が求められ,指導的立場とみなされることが日米における専門医の大きな違いである.そのため給与面の待遇もトレーニング前後で5~10倍に上昇するが,それだけ厳しいトレーニングを受けたことと専門医取得者の社会的責任を反映していることにほかならない.
また国内では外科専攻医の期間でサブスペシャルティ研修もオーバーラップして行うことが可能となっており,これは米国で導入が始まりつつある一般外科と小児外科を統合したレジデンシープログラムに近い研修システムである.ただ前提として外科専門医・小児外科専門医のどちらも,米国では限られたレジデント・フェロー枠を目指してしのぎを削る状況にある.特に小児外科フェロー枠は年間40程度であり,外科レジデントを終了してABSのBoard Certificateを取得した精鋭が小児外科のBoard Certificateの取得を目指す.フェロー枠が制限されているのは,経験症例数を担保するだけでなく,小児外科専門医の総数もある程度コントロールする意味もあり,患者が集約されるため施設あたりの症例数も国内の10倍以上となり,提供される小児外科手術・医療の質も担保される.
国内では外科・小児外科とも採用可能な専攻医数の制限は実質的になく,希望すればプログラム・カリキュラムに入ることが可能である.現在国内小児外科施設が約200前後あり,患者にとっては非常にアクセスのよい医療システムではあるが,研修する専攻医には充分な経験症例数が得られない,あるいは地域や施設によって偏りが生じるなどの問題点もある.また国内において加速度的に進みつつある少子化により,小児外科症例の減少が避けられない状況にあり,質を担保した小児外科専門医の教育と育成を行うにあたって,患者集約や施設の層別化などの議論を真剣に進める必要がある.
V.北米における外科教育研究と国内における外科教育研究(倉島 庸)
[北米における外科教育研究の変遷]
外科教育分野で世界をリードする北米のアカデミアから,外科教育研究論文の報告数が急速に増加したのは1990年代後半から2000年代に遡る.この時期は内視鏡外科手術の創成期と,シミュレーショントレーニングが外科トレーニングに普及し始めたタイミングに重なる.エビデンスに基づいた外科医の技能評価法,新たな手術手技トレーニング法開発のニーズにより,この時期は内視鏡外科手技練習用のボックストレーナーを使用した研究や,手術中のパフォーマンス評価,トレーニング法に関する研究が盛んに行われた.2000年以降になると米国の外科教育はアウトカム重視の教育方略,すなわちCompetency-based education(能力を基盤とした教育),Goal-directed training(目標を目指したトレーニング)にシフトした外科研修システムへとシフトし,外科医の自律性やマイルストーンに沿った研修カリキュラム開発など,研修システムに関わる研究も行われるようになった.
[北米の外科教育学会]
北米の外科教育システムおよび研究の発展に大きく貢献した学会が,1977年設立のAPDS (Association of Program Directors in Surgery:プログラムディレクター学会)5)と1980年設立のASE (Association for Surgical Education:外科教育学会)6)である.APDSは米国内の外科研修責任者および外科研修医のサポートを目的とし,2016年からはACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education,米国卒後医学教育認定評議会)7)のプログラム監修組織として公式認定されている.また,ASEは外科教育研究促進と外科指導者の育成を目指した学会である.APDS,ASEはそれぞれの学術集会および学会誌から外科教育研究成果の公表に加えて,外科教育専門学会として外科系主要学会や外科研修,専門医制度に関わる組織の業務支援や試験・認定制度へのエビデンス提供に大きく貢献している.
[日本の外科教育学会と外科教育研究]
わが国では外科教育の専門組織として,2014年に日本外科教育学会 (JASE: Japanese Association for Surgical Education)8)が設立された.学会の目的は,1. 外科教育の人材育成,2. 外科教育の方略開発,3. 外科教育研究促進により外科医療の質向上に貢献することである.学会の主な活動は,毎年開催される学術集会Surgical Education Summit (SES)である.SESではさまざまな施設から外科教育に関する試みと成果が報告され,活発な議論が交わされてきた.また2019年からは年2回各4日間の日程で外科指導者講習会を主催してきた9).近年,日本外科教育学会学術集会や外科指導者講習会の参加者が各施設で外科教育研究に取り組み,専門とする臨床系学会学術集会でその成果発表や,学会主催者側として外科教育セッションの企画に関わるなど,日本国内の外科教育研究の普及に一定の貢献をしていると思われる.今後,わが国における外科教育研究分野の課題は,日本発の外科教育研究のエビデンス発信と,APDS・ASEのような外科系主要学会との協働による国内の外科教育システム改善への貢献である.
[これからの外科教育研究]
外科教育研究のテーマは外科学の進歩と切り離せないため,今後はロボット支援下手術や人工知能などのテクノロジーを利用した教育研究が発展するであろう.また,国際規模で外科医不足と外科医の過酷な労働環境が指摘される中,外科医のキャリア形成,外科研修環境,外科医のwell-beingに関する大規模サーベイや質的研究の重要性が増すであろう.
VI.おわりに
今回本邦と米国における外科専門医・小児外科専門医の教育体制と外科教育研究を対比した.医療システムや保険制度の異なる状況で優劣を論ずることはできないが,双方において優れた点があり,社会や時代の変化に対応しつつ,良質な外科医療を提供できる専門医育成を目指すべきである.また北米で先行していた外科教育研究も,国内でも日本外科教育学会7)として発足し,今後はわが国発の外科医教育の指導手法やプログラム・カリキュラムの策定,そして教育を科学するという観点での発展が期待される.
利益相反:なし
文献
1) 一般社団法人日本専門医機構ホームページ.2024年4月8日. https://jmsb.or.jp/
2) 一般社団法人日本外科学会ホームページ.2024年4月8日. https://jp.jssoc.or.jp/
3) 一般社団法人日本小児外科学会ホームページ.2024年4月8日. http://www.jsps.or.jp/
4) American Board of Surgery.2024年4月8日. https://www.absurgery.org/
5) Association of Program Directors in Surgery.2024年4月8日. https://www.apds.org/
6) Association for Surgical Education.2024年4月8日. https://www.surgicaleducation.com/
7) Accreditation Council for Graduate Medical Education.2024年4月8日. https://www.acgme.org/
8) 日本外科教育学会ホームページ.2024年4月8日. https://www.surgicaleducation.jp/
9) 日本外科教育学会ホームページ.2024年4月8日. https://www.surgicaleducation.jp/SAE.html
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。