日外会誌. 124(1): 18-24, 2023
特集
独自の進歩を見せる日本の甲状腺癌治療学
3.甲状腺乳頭癌のリスク分類とそれに応じた取り扱い方針
|
1) 隈病院 外科 伊藤 康弘1) , 宮内 昭1) , 赤水 尚史2) |
甲状腺乳頭癌は概ね予後良好であるが,一部に再発を来して患者の生命を脅かす症例が存在する.どういう症例が予後不良となりうるのかを,初期治療の段階で見極めることが非常に重要である.日本内分泌外科学会編の「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」では乳頭癌の予後に応じて以下のように,リスク分類を行っている.すなわち,1)超低リスク T1aN0M0, 2)低リスク T1bN0M0,3)高リスク 4 cmを越える腫瘍径,Ex2に相当する腺外浸潤またはリンパ節節外浸潤,3 cmを越える転移リンパ節,臨床的な遠隔転移のうち一つ以上を有するもの,そして4)中リスク 1)〜3)のどれにも該当しない症例である.しかし,この分類には重要な予後因子である年齢が入っておらず,55歳を年齢カットオフ値として解析すると,疾患関連予後は超低/低リスク症例,若年者の中リスク症例,高齢者の中リスク症例および若年者の高リスク症例(この二群間の予後に有意差なし),そして高齢者の高リスク症例の順に不良であった.超低/低リスク症例は年齢に関係なく予後良好であるので過度に広範囲な手術は行うべきではない.若年者の中リスク症例である程度遠隔再発の可能性ありと考えられる場合は,再発発見とその場合の対応を考え甲状腺全摘を施行することが望ましいであろう.高齢者の高リスク症例の治療は認知機能,全身状態(performance statusなど)を考慮して個別に判断すべきである.
キーワード
甲状腺乳頭癌, 予後, リスク分類, 治療
I.はじめに
甲状腺乳頭癌は甲状腺悪性腫瘍の中でもっとも頻度が高く,日本では全体のほぼ90%を占める.ほとんどの症例は進行が緩除であり,従って適切に対応すれば予後は良好である.しかし一部の症例は転移再発を繰り返し,その再発巣のコントロールが困難になった結果,予後不良の転帰をとる.治療する側としては,どういう臨床病理学的因子を持つ症例の予後が特に不良であるのかをきちんと把握しておく必要がある.
甲状腺乳頭癌の治療戦略は,元々欧米と日本でかなり異なっていた.欧米では基本的に甲状腺全摘を施行し,その後は放射性ヨウ素(RAI)によるアブレーション,そして甲状腺刺激ホルモン抑制をほぼ画一的に施行していた.日本では逆に,かなり進行した症例にもできるだけ甲状腺を残す手術を行い,その代わりにリンパ節郭清を広範囲に行ってきた.両者の戦略には一長一短がある.前者は全摘やましてやRAI治療など必要ない症例に,過剰な治療をしてしまうことになる.また後者は,転移再発を来しやすい症例に対しても手控えた手術を行ってしまい,次の治療が遅れて予後を悪くしてしまう可能性がある.
2010年,当時の日本内分泌外科学会および日本甲状腺外科学会は「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」を作成し,2018年に改訂版が出された1).そこでは乳頭癌を術前および術中所見によってリスク分類を行い,どういう症例が危険なのか,どういう症例に甲状腺全摘や予防的郭清を行い,再発に備えるべきなのかを述べた.今回はその分類の妥当性について検討するとともに,さらなる改善点についても言及したい.
II.甲状腺乳頭癌の予後因子
甲状腺乳頭癌の予後因子は,その評価する時期によっていくつかに分類される.
以下に概要を述べる.
1)術前に評価できる予後因子
患者の背景および術前の画像検査で評価できるもので,年齢,性別,腫瘍径,臨床的なリンパ節転移,遠隔転移が挙げられる.それぞれが予後因子となり,Tumor-node-metastasis (TNM) staging system2)に性別以外採用されている.
2)術中に評価できる予後因子
手術中に評価するべきもので,原発巣の被膜外進展が重要な所見である.TNM staging systemには採用されていないが転移リンパ節からの節外浸潤も,頻度は原発巣に比べて低いながらも重要な予後因子である.
今回のテーマであるリスク分類は,上記の1)と2)を組み合わせたものである.
3)術後病理所見に基づく予後因子
乳頭癌には様々な亜型があり,その中には予後不良とされるものがある.びまん性硬化型,高細胞型,ホブネイル型などがそれに当たり3),これらについては術後慎重な経過観察が必要である.また,細胞増殖能の指標となるKi-67 labeling indexが高い症例の予後が,不良であることもわかっている4).
4)分子病理学的な予後因子
BRAF遺伝子とTERT遺伝子の両方に変異のある症例は予後不良であることがわかっている.本邦からもTERT遺伝子を解析した論文が出ている5).
5)術後経過観察中に分かる予後因子
甲状腺全摘を施行された抗サイログロブリン抗体陰性患者の場合,サイログロブリン値の推移が予後を反映する.サイログロブリン倍加率/倍加時間が1(/年)以上/1年以下の症例は,生命予後不良である6).また,転移巣の体積倍加率も同様に予後を強く反映する7).抗サイログロブリン抗体が陽性である患者においては,全摘術後に抗体価が50%以上低下した症例の予後は良好であり,低下しない症例の予後は不良の傾向がある8).さらに遠隔転移がすでにある症例において,好中球/リンパ球比が3を超える症例も,生命予後不良である7).
III.甲状腺乳頭癌のリスク分類
2018年に改訂されたガイドラインでは,乳頭癌において術前術中の予後因子をふまえたリスク分類を提示している1).表1にその概要を示す.超低リスクはいわゆる低リスク微小癌で,積極的経過観察の適応となる.手術を施行した場合,超低リスクと低リスク症例の予後は変わらない.高リスクは4センチを超える腫瘍径,「甲状腺癌取扱い規約」における原発巣および転移リンパ節からのEx2相当の浸潤,3センチを超えるリンパ節転移9),遠隔転移のうちどれかを含む症例ということであるが,これらは特別な事情がない限り甲状腺全摘の適応となる因子である.中リスクはそれ以外のいずれにも該当しない症例ということで,腫瘍径が2.1~4 cm, 3 cm以下のリンパ節転移,Ex1相当(すなわち前頚筋群)の浸潤のどれかがある症例ということになる.
われわれはまず,このリスク分類が本当に予後を反映するのかを検討した10).図1に超低/低リスク,中リスク,高リスク症例のリンパ節再発予後,遠隔再発予後,疾患関連予後についてのKaplan-Meier曲線を示した.いずれの予後も超低/低リスク,中リスク,高リスクの順に有意に不良という結果が得られた.従ってこのクラス分類は,乳頭癌症例の予後を的確に反映するものであると言える.

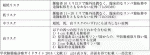
IV.予後因子としての年齢
ガイドラインのリスク分類は,乳頭癌患者の予後をよく反映することがわかった.しかしこの分類には,重要な予後因子である年齢が組み込まれていない.年齢が予後を強く反映することは周知の事実であり,TNM staging systemにおいても55歳未満は遠隔転移がなければすべてStage Ⅰに分類され,遠隔転移があってもStage Ⅱに分類されているがこれは若年者の生命予後が非常に良いためである.
しかし若年者の予後は,すべてにわたってよいというわけではない.表2は年齢に30歳と60歳の二つのカットオフ値を設け,それぞれの予後を検討したものである11).表2aおよび表2bを見ると60歳以上だけではなく,30歳未満の症例の局所および遠隔再発予後は中年者に比べて有意に不良であることがわかる.一方で表2cに示すように,高齢者の疾患関連予後は不良であるが若年者のそれは不良ではない.これは若年者の再発巣は手術や放射性ヨウ素治療によって比較的容易にコントロールできることが多いが,高齢者の場合は局所再発も浸潤性が強く,遠隔再発巣も放射性ヨウ素抵抗性のことが多くコントロールが困難であるためと考えられる.
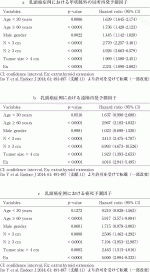
V.年齢を加味したリスク分類
上記のことをふまえて,ガイドラインのリスク分類に年齢を加えて検討した12).まず超低/低リスク症例についてであるが,これらの予後は年齢の影響を全くうけない.すなわち年齢に関係なく超低/低リスク症例は,予後良好である.次に中リスクおよび高リスク症例の疾患関連生命予後と年齢の関係を検討した.年齢のカットオフはUICC TNM staging systemに従って,55歳とした.図2にその結果を示す.高リスク症例および中リスク症例とも55歳以上のサブセットは55歳未満のそれよりも,有意に疾患関連予後は不良であった.そして55歳未満の高リスク症例の予後は,55歳以上の中リスク症例と変わらなかった.
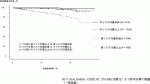
VI.新しいリスク分類と治療方針
確かに現在のリスク分類は,予後をよく反映する.しかしそこへ年齢を加えると,この分類が本当に妥当かどうかは疑問である.まず,高リスクの高齢者の予後は他群に比べて非常に悪い.次いで中リスクの高齢者と高リスクの若年者の予後が不良であり,中リスク若年者の予後は比較的よいが,それでも超低/低リスク症例よりも悪いという結果であった.従って,高齢者の高リスク,若年者の高リスクと高齢者の中リスク,若年者の中リスク,そして年齢に関係なく超低/低リスクという風に,四つに分類するのが妥当と考えられる.
各リスクの症例をどう治療していくかについては,現時点でガイドラインが改訂中であるため詳述するのは不適切と考えるが,少なくとも超低/低リスク症例に対して,甲状腺全摘および広範囲な頸部郭清などの過剰な治療は勧められない.治療による有害事象やQuality of lifeの低下といったデメリットが,あきらかにメリットを上回ると考えられる.現時点では遠隔再発を来した場合,治療の第1選択はRAI治療である.RAI治療は特に若年者に奏効するというのは,周知の事実である.従って遠隔再発を来す危険性がある程度あると判断された若年者の高リスク症例や一部の中リスク症例に対しては,速やかにRAI治療を行えるように初回手術で全摘を施行するべきである.高齢者の高リスク症例は再発のみならず癌死のリスクも高いので,RAI治療そして分子標的薬投与にそなえて本来は全摘をきちんと行うのが望ましい.しかし,認知機能も含めた全身状態や平均余命などをきちんと評価し,個別に治療方針を決定するのが現実的であり妥当と思われる.
VII.おわりに
日本内分泌外科学会のガイドラインに基づく,甲状腺乳頭癌のリスク分類について詳述した.われわれは,どういう症例に再発あるいは癌死のリスクが高いのかをきちんと認識して診療に当たらなくてはならない.
利益相反:なし
文献
1) 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会編:甲状腺腫瘍診療ガイドライン.金原出版,東京,2010.
2) Brierley JD, Mary K, Wittekind C, et al.: TNM classification of malignant tumours, 8th edition. Wiley, New York, 2017.
3) 日本内分泌外科学会・日本甲状腺病理学会編:甲状腺癌取扱い規約.金原出版,東京,2019.
4) Ito Y, Miyauchi A, Kakudo K, et al.: Prognostic significance of Ki-67 labeling index in papillary thyroid carcinoma. World J Surg, 34: 3015-3021, 2010.
5) Ebina A, Togashi Y, Baba S, et al.: TERT promoter mutation and extent of thyroidectomy in patients with 1-4 cm intrathyroidal papillary carcinoma. Cancers (Basel), 12: 2115, 2020.
6) Miyauchi A, Kudo T, Miya A, et al.: Prognostic impact of serum thyroglobulin doubling-time under thyrotropin suppression in patients with papillary thyroid carcinoma who underwent total thyroidectomy. Thyroid, 21:707-716, 2011.
7) Ito Y, Onoda N, Kihara M, et al.: Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in differentiated thyroid carcinoma having distant metastasis:A comparison with thyroglobulin-doubling rate and tumor volume-doubling rate. In Vivo, 35: 1125-1132, 2021.
8) Tsushima Y, Miyauchi A, Ito Y, et al.: Prognostic significance of changes in serum thyroglobulin antibody levels of pre- and post-total thyroidectomy in thyroglobulin antibody-positive papillary thyroid carcinoma patients. Endocr J, 60:871-876, 2013.
9) Sugitani I, Kanai N, Fujimoto Y, et al.: A novel classification system for patients with PTC:addition of the new variables of large (3 cm or greater) nodal metastases and reclassification during the follow-up period. Surgery, 135: 139-146, 2004.
10) Ito Y, Miyauchi A, Oda H, et al.: Appropriateness of the revised Japanese guidelines’ risk classification for the prognosis of papillary thyroid carcinoma: a retrospective analysis of 5,845 papillary thyroid carcinoma patients. Endocr J, 66: 127-134, 2019.
11) Ito Y, Miyauchi A, Kihara M, et al.: Prognostic significance of young age in papillary thyroid carcinoma: analysis of 5,733 patients with 150 months’ median follow-up. Endocr J, 61: 491-497, 2014.
12) Ito Y, Miyauchi A, Yamamoto M, et al.: Subset analysis of the Japanese risk classification guidelines for papillary thyroid carcinoma. Endocr J, 67: 275-282, 2020.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。