日外会誌. 121(3): 329-333, 2020
会員のための企画
全身用立位CTの開発と臨床応用―健康長寿の時代を迎えた今,機能異常の早期発見を目指して―
|
1) 慶應義塾大学 医学部放射線科 陣崎 雅弘1) , 山田 祥岳1) , 横山 陽一1) , 名倉 武雄2) , 成田 啓一1) , 中原 健裕1) , 山田 稔1) |
立位CT(Computed Tomography)の第1号機が,当院に導入された.立位CTは1972年にCTが開発された直後から発想されていたが,当時のCTは撮影時間が非常に長く,立位の姿勢で安静を保つことが難しかったため,実現してこなかった.近年,CTの撮影時間が大幅に短縮したため,立位でのCTが実現可能と考え,企業と共同で立位CTを開発した.
導入後に,このCTは,従来の臥位CTと同等の物理特性を持ち,正確な上下運動により臨床で使用可能な画質を担保できていることを検証した.また,必要な設置面積が従来のCTの3分の2で済み,また,ガントリーに入ればすぐに撮影を開始できるので,X線撮影のようなワークフローで検査が行えることがわかった.
健常人での検討では,静脈の体位による変化が部位により異なることがわかり,今後画像での静脈学を構築する端緒についたと思う.また,これまで脳や骨盤は体位により位置が変化しないとされてきたが,われわれの検討では正常人でも立位で下垂していることがわかり,重力下の人体の構造が少しずつ明らかになってきている.現在,疾患への応用を始めたところで,運動器疾患,ヘルニア・臓器脱などは定量的に評価可能であることを明らかにした.また,嚥下・呼吸・排尿・歩行機能などの様々な機能の解明とそれに関連する病態の早期発見に有用な所見の検討,更には加齢性変化も検討しており,健康長寿の時代のニーズに貢献できることを目指したい.
キーワード
立位, 臥位, 重力, X線, Computed Tomography
I.はじめに
時代によって,政策的・学術的に重視される疾患は変わる.1970年代までは結核を主体とした感染症,1980年代はがん,1990年代は動脈硬化,2000年代は生活習慣病であり,この頃までは器質的疾患が主対象であった.2010年代に入り慢性閉塞性肺疾患,そして最近ではロコモティブシンドロームになり,機能的疾患が対象となってきた.
CT/MRIなどの横断像が撮れる画像診断は,これまで臥位撮影で器質的疾患の定量・定性評価を担い,生命予後の改善に貢献することを目標としてきた.最近,超高齢化社会を迎え,機能を保ち健康長寿を実現することが重要になった.機能の多くは立位で行われるため,立位で機能を定量評価できる機器の開発が必要と考えた.そこでわれわれは,メーカーと共にUpright CT(以下,立位CT)の開発を進め,実機を完成させ,当院に導入した.これにより重力の影響下の人体を横断像で可視化できるようになった1).
本稿では,立位CTの開発の経緯,性能,明らかになってきたことについて概説する.
II.歴史的背景
近年,CTを始めとする画像診断機器は長足の進歩を遂げている.1990年代のCTは,1回転で5mm厚程度の1枚の画像のみを撮影し,2次元画像としての診断をしていた.1998年に1回転で4スライスの画像を撮影できる多列検出器CTが,2000年代中頃には1回転で64スライス撮れるCTが登場した2).この機種では,0.5mm程度の薄いスライス厚で広範囲に撮影することが可能で,3次元像を作成しても高画質であった.このため,3次元での診断が普及し始め,当時行われていた血管造影,排泄性尿路造影,胆道造影,注腸造影といった造影X線検査が,3次元CT検査に置き換わっていった3)4).2010年頃になると,320列のCTが登場し,頭尾方向に16cmの幅を1回転で撮影でき,同じ場所を連続撮影すると4次元診断(3次元像の時間的変化)が可能になった.16cm幅では,脳,心臓,肝臓,腎臓や多くの関節の機能的診断を行うことができ,CTが形態から機能評価の時代に移行したことを実感した5)6).
このようなCTの進歩をみてきて,二つのことを考えた.一つは,人体の機能には,嚥下,呼吸,排尿,歩行など立位のみで可能なものが多くあるため,立位の4次元診断が必要な時代になるのではと思った.特に,機能的疾患の早期発見は,健康長寿に必須であるため,時代のニーズに合致すると思った.もう一つは,造影X線検査は置換されたが,胸部の単純X線検査はいつまで残るのだろうかと思った.胸部単純X線検査は,立ったままの撮影で多くの検査をこなすことができ,心不全の程度評価のように立位評価が必要な病態には向いているが,がんの検出精度は高くなく,定量評価も困難である.立位CTであれば,これらの課題を克服し,胸部X線検査の役割を高い精度で代替できるのではと考えた.
立位撮影を想定した場合の最大の課題は撮影時間で,2000年代初頭までは臥位CTで躯幹全長を撮影するのに1分近くかかっており,立位の体勢で患者が静止し続けることに難があると予想された.64列CTが登場したころから,躯幹全長を20秒くらいで撮影できるようになり,立位CTの実現の可能性があると感じた.
III.開発の経緯
立位で3次元診断可能なものとしてはCone beam型CTが先行して存在していたが,1回転にかかる時間がCTの10倍以上であり,軟部組織のコントラストが十分でなく,骨や歯に限定された.また,立位で撮影可能なupright MRが開発された時期があったが,撮影時間がCTよりはるかに長く,座位での評価が主体であった.また,スライス厚が5mm程度とCTの10倍厚く,3次元での評価ができなかった.
一方,CTは前述の様に,2010年代には20秒程度で躯幹全長の3次元撮影できるようになっていたので,われわれは国内大手企業(キヤノンメディカルシステムズ株式会社)に立位CTを提案し,共同で立位CTの開発に取り組んだ.ガントリーを左右の支持器で支え,この支持部分が上下することで水平にup-downする構造にし,転倒防止装置や姿勢保持の補助具なども開発し,2年後に臨床導入可能な実機が完成し,当院に世界第1号機が導入された(図1).この装置は320列で,通常のヘリカル撮影に加え,16cm幅の4次元画像を撮ることもできる.また,設置面積が従来のCTの3分の2程度になり,X線装置と同じくらいのスペースで済むようになった.

IV.物理的性能評価
導入後,まず性能評価を行い,空間分解能やノイズ特性が従来の臥位CTとほぼ同等であった1).ガントリーの左右の支えの上下運動に少しでもズレが生じると,画像が歪むことになる.通常の臥位CTは,患者の乗った台が頭尾方向に動くので,画質に歪みが生じない.立位CTの物理特性が臥位CTと全く同等であったということは,ガントリーが正確に上下運動を出来ているということであり,日本企業の技術力の高さを印象づけられるものであった.
V.ワークフローの改善
実際に人の撮影を始めて最初に気づいたことは,立位CTの撮影のワークフローが格段に良いことである.立位CTにおいては,ガントリーの中に入ればすぐに撮影が開始できるので,X線撮影に似ている.それに対し,臥位CTはテーブルに乗り,台をガントリーに入れるという手間が必要になる.実際に計測すると,入室から撮影開始までと撮影終了から退出までの時間を足すと(検査総時間から撮影時間を引いたもの),立位CTでは40秒程度で,立位CTでは撮影以外にかかる時間が非常に短くて済む1).上記の様に設置面積が小さくて済むことを考えると,スペースやワークフローの観点からはX線の代わりになる可能性を持っている.
VI.体位により変化する解剖構造~静脈学の構築へ
健常人で重力下の人体の影響を調べたところ,多くの臓器の解剖学的構造が体位により変化することがわかったが,最も印象的であったのが静脈である.静脈径は,心臓より上部では臥位と比較して立位で最大80%縮小し(図2),横隔膜の高さでは変わらず,下大静脈では最大40%程度拡張しており,心臓との位置関係で状況が変化することがわかった1).これは心臓を基準とした静水圧の影響と思われた.ちなみに,上大静脈はこれまで評価法がなく,径の体位変化は初めて評価できた.一方,動脈径は部位によりまったく変化しなかった.更に興味深いことに,頭蓋内の静脈径は,体位により変化せず,頭蓋内は恒常性が保たれていることがわかった.
あらゆる臓器に循環系が存在し,これまで動脈系と微小循環系(虚血評価)は画像で評価できていたが,静脈の可視化は超音波で検査できる範囲に限られ,ほとんどできていなかった.今後,流出路の解明が進むことにより,ようやく画像での静脈学が構築されていくのではないかと考えている.
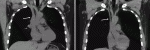
VII.体位により変化する事が新たにわかった解剖構造
これまで立位のMRでの検討で,脳や骨盤底は動かないとされてきた.しかし,立位のCTで検討すると,これらの臓器は動いていることがわかった.脳はわずかであるが立位で前下方に動いており,これは当時のMRのスライス厚が5mmであったのに対し,今回のCTは0.5mmであり,はるかに高い分解能になっているためと思われる.最近,宇宙に行った宇宙飛行士の脳が,上方へ変位していることが報告され,脳が動くということが関心を持たれているが,地球においても脳は体位により変動していることがわかった.
骨盤底については,座位での検討しかなく,臥位と比べて変化しないとされてきた.しかし,今回立位で撮影すると,臥位に比べて健常人でも下垂していることがわかった.しかも女性のほうが男性よりも下垂しており1),更には加齢とともに下垂することがわかった.高齢女性に排尿障害が多いこととの関連があると思われる.
肺は,立位では臥位に比べて全容積が10%程度増大しており,上葉よりも下葉の変化率が大きく,中葉はほとんど容積が変化しないことがわかった.
VIII.疾患
これまで健常人データの取得を主に行ってきたので,これから疾患に対しても臨床研究を行っていく予定である.
立位で症状が増悪する疾患に有用で,脊椎すべり症,骨盤脱(図3),ヘルニア疾患などは重症度を定量的に評価できること1),変形性膝関節症などの早期発見にも有用であることがわかってきた.乳がんの乳房摘出術前において健側の形状を評価することにも有用である.
現在,静脈の検討として,心不全の定量化,下肢静脈瘤の病態評価などを考えており,また嚥下機能を評価し,誤嚥性肺炎の定量化も検討する.呼吸機能の評価,排尿機能も検討中で,興味深い結果が得られそうである.
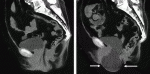
IX.おわりに
以上,立位CTの開発の経緯とこれまでの検討内容を述べてきた.これから数年かけて様々な機能的疾患の病態解明や早期発見に役立つ手がかりを検討し,健康長寿の時代のニーズに貢献できることを目指したい.読者の皆様からも,このような検討が可能ではないかというご意見を頂ければ幸いである.
利益相反
研究費:キヤノンメディカルシステムズ株式会社
文献
1) Jinzaki M, Yamada Y, Nagura T, et al.: Development of Upright Computed Tomography With Area Detector for Whole-Body Scans:Phantom Study, Efficacy on Workflow, Effect of Gravity on Human Body, and Potential Clinical Impact. Invest Radiol, 55(2): 78-83, 2020.
2) Hu H: Multi-slice helical CT:scan and reconstruction. Med Phys, 26: 5-18, 1999.
3) Jinzaki M, Matsumoto K, Kikuchi E, et al.: Comparison of CT urography and excretory urography in the detection and localization of urothelial carcinoma of the upper urinary tract. AJR Am J Roentgenol, 196: 1102-1109, 2011.
4) Halligan S, Wooldrage K, Dadswell E, et al.: Computed tomographic colonography versus barium enema for diagnosis of colorectal cancer or large polyps in symptomatic patients (SIGGAR):a multicentre randomised trial. Lancet, 381(9873): 1185-1193, 2013.
5) Fujiwara H, Momoshima S, Akiyama T, et al.: Whole-brain CT digital subtraction angiography of cerebral dural arteriovenous fistula using 320-detector row CT. Neuroradiology, 55: 837-843, 2013.
6) Sakamoto Y, Soga S, Jinzaki M, et al.: Evaluation of velopharyngeal closure by 4D imaging using 320-detector-row computed tomography. J Plast Reconstr Aesthet Surg, 68: 479-484, 2015.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。