日外会誌. 125(3): 207-215, 2024
特集
Acute Care Surgeon―その活躍の場―
3.多数傷病者事案mass casualty incident(MCI)における活躍
|
1) 日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急科 井上 潤一1)2) , 大友 康裕2) , 庄古 知久2) , 森下 幸治2) , 松島 一英2) , 比良 英司2) , 溝端 康光2) , 渡部 広明2) , 中田 孝明2) , 松原 久裕2) |
Acute Care Surgeonは日々の外傷診療から災害対応に必要な状況に応じた判断力と実行力そしてチームをまとめるリーダーシップを経験的に習得するとともに,救急外来や手術室,集中治療室等のいわゆる災害時初動部門を日常的に活動の場としている.したがって外傷患者が多く発生する多数傷病者事案mass casualty incident (MCI)においてAcute Care Surgeonはトリアージや治療に加え対応全般を統括するリーダーに適した人材となりうる.日本外科学会では東京オリンピック・パラリンピックでの銃創・爆傷診療への備えとして2017年度より外科専門医を対象とした「外傷外科医養成研修」を開催しこれまでに医師看護師あわせて536名が修了.昨年のG7広島サミットでは研修修了者のAcute Care Surgeonからなる外傷外科チームTrauma Surgical Assistant Team (TSAT)を組織し初めて広島県内の2施設に派遣,サミット期間中の首脳外傷対応ならびにMCIを含む救急災害医療体制の支援を行った.今後学会としてTSATを養成し大規模イベントや災害への派遣を行う方針である.Acute Care Surgeryが扱う外傷外科,救急外科,外科的集中治療,surgical rescue の四つの柱に加え,MCIを含む災害対応を五つ目の柱とすることがAcute Care Surgeonの職域とidentityを確立するとともに,わが国の外傷外科診療ならびに救急災害医療体制の強化に寄与することが期待される.
キーワード
MCI, TSAT, 外傷外科医等養成研修, Acute Care Surgeon, Acute Care Surgery
I.はじめに
鉄道事故やテロなどにより同時に多数の傷病者が発生することを多数傷病者事故mass casualty incident (MCI)という.限定した地域で発生し急増した医療需要が一時的に供給を上回ることから局地災害とも呼ばれる.とくに近年では銃や爆発物によるテロ事案のリスクが懸念されており多数の銃創や切創,爆傷患者への対応が喫緊の課題となっている.米国では2001年の同時多発テロを受け米国外科学会はそれまでの無関心を改め積極的に災害および多数傷病者対応に関わることを外科医の責務とする声明を発表1),現在では実地とオンラインでの災害医療研修コースを展開している2).わが国ではこれまで救急医を中心にMCIへの対応を行ってきたが,銃創や爆傷などの重症外傷を対象とすることから外科医,なかでも日常的に外傷の診療にあたるAcute Care Surgeonの関与が重要となっている.本稿ではAcute Care SurgeonとMCIとの関係,日本外科学会による外傷外科医等養成研修と昨年発足した外傷外科チームTrauma Surgical Assistance Team(TSAT)の概要と広島G7での活動,今後のAcute Care SurgeryにおけるMCIへの展望について述べたい.
II.Acute Care SurgeonとMCI
米国では1980年代から数々のテロを経験し,また銃乱射によるMCIが各地で発生することを受け米国外科学会は2003年に外科医が災害時やMCIにおいて指導的役割を担うことを声明文“Statement on Disaster and Mass casualty Management”として社会に発出している.この背景には「大量殺傷事件や災害を,いつも遠くで起こる頻度の低い大惨事とみなしていた.防災訓練は厄介なものであり,不必要な事務処理訓練と見なされていた.」という状況への危機感があった3).声明文の中では外傷外科医は複数の患者に対するトリアージと迅速な意思決定にもとづく治療を日常的に行っていること,また病院前救急医療体制や外傷診療体制に関わる点からもMCIに関与することを期待されている.
これを受け,MCIや災害において外傷外科医はトリアージや治療にとどまらず病院全体の対応において重要な責務があること4),外科医は自然災害を含むall hazardsに対し院内にとどまらず地域社会において準備や計画段階から関与すべきであること5),また戦傷外傷での経験を市中で発生するMCIに還元すること6)など,災害対応において外科医が積極的に関与することが報告されるようになった.その一方で外科医は救急医に比べ災害医療に関する理解度が低いこと,にもかかわらず自分はリーダーになれると考えているものが多いことから教育や訓練の重要性が指摘されている7).
わが国は先進国の中でも特に災害が多い国であるが,災害対応はおもに救急医を中心に行われてきた.災害時の外傷診療も同様に救急医が担う場合が多く,外科医は自らが災害に直面して初めてその実際に触れるということも少なくなかった.この背景には外科医は予定手術や毎週の外来診療があることから災害に関する研修会への参加や実災害への派遣が容易ではないことも関係していると思われる.
このような状況で第119回日本外科学会定期学術集会のパネルディスカッション「災害医療における外科医の役割」では重症外傷診療に従事する機会の多いAcute Care Surgeonが災害医療を担うという報告が自施設の経験をふまえ複数の施設から報告された.下條らは通常業務としてプレホスピタルから初期診療,集中治療を含めた根本治療を担うAcute Care Surgeonが,災害対応計画,訓練,実働の中心となること,外傷診療の延長線上に災害医療があると捉えAcute Care Surgeryの担う一領域であると述べている8).益子らは災害やテロを「外科的緊急事態」と捉えAcute Care Surgeryは院内外の外科的リスクに対応するための「外科的危機管理部門」として最適の存在であると述べている9).岡田らはAcute Care Surgeonは災害時に外傷手術を行う高度技能医としての役割とともに,初療室,手術室,集中治療室を日常の診療エリアとするAcute Care Surgeonが災害時の現場診療をマネジメントする外傷リーダーとして適任であると述べている10).
細分化・専門化が今後も進むと思われる外科の現状において,日々の外傷診療から組織横断的・俯瞰的に活動するAcute Care SurgeonはそのリーダーシップとともにMCI対応を担うことに適した人材と考えられる.
III.外傷外科医等養成研修事業とTSAT
【外傷外科医等養成研修】
体幹外傷手術とそれに伴う外科的集中治療がAcute Care Surgeonの主要な領域であるという認識が徐々に広まるなかで,東京オリンピック・パラリンピックにおける銃・爆発物によるテロ災害への対応が喫緊の課題となった.わが国ではこれらの外傷の診療経験が乏しいことから厚生労働省は2017年度より銃創,切創,爆傷等の診療を担う医師看護師等をチームとして育成する「外傷外科医養成研修事業」を開始,日本外科学会が実施団体として選定され専門医制度委員会の下部に「外傷外科医養成研修実施委員会」を設置し毎年度研修会を開催してきた.これまでに7回開催(東京6回,コロナ禍でのWeb開催1回),全国の医師看護師536名(医師269人,看護師267人)が修了している.
受講資格は救命救急センターを有する施設に勤務する日本外科学会専門医と看護師のペアとし, 医師は5年間 350 例以上(うち術者で120 例)の手術経験を,看護師は手術室もしくは救急外来に5年以上勤務し,かつ実際に外傷手術に携わった経験があるものとし,臨床面で一定以上の水準をクリアすることを条件としている.さらにサミットなどの国際会合,オリンピックやワールドカップなどの大規模スポーツ大会での医療体制協力要請や,外傷患者が多数発生する事態への招集に積極的に協力できることとしている.
研修プログラムは,同委員会によって検討され1)外傷外科実技コース(ブタを用いた外傷外科手術治療戦略(SSTT)コース11),または献体を用いた Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma(ASSET)コース12))のいずれかの受講,2)事前eラーニングの視聴,そして仕上げとなる3)グループディスカッションを中心とした集合研修の3パートからなる.
eラーニングを含む座学では外傷外科総論,爆傷の病態生理,銃創と弾道学,過去の海外のテロ災害事例,銃創の外科治療,救援者のメンタルヘルスケア,外傷外科看護などが講義され,グループディスカッションでは外傷ケーススタディー,チームマネージメント(ブリーフィング,デブリーフィング,大量輸血プロトコールなどを含む),多数傷病者対応等についてディスカッションを通して学ぶ内容になっている(図1).
さらに受講者には事前に外傷緊急手術体制のアンケート調査を実施し自施設の課題を把握したうえで本研修会に参加することとし,研修修了後3カ月以内に「院内体制の変化」についてのレポート提出を義務づけ各病院の体制整備を促す形を取っている.
インストラクターはわが国の第一線で活躍するAcute Care Surgeonと本研修の修了者からなるタスクスタッフが担当,さらに今年度は麻酔科医が試行的にオブザーバー参加し手術を中心としたチームとしての外傷診療体制を学ぶものとなっている(図2).
研修会終了後のアンケートでは受講生の8割以上が「役に立つ(5段階評価で5)」,「概ね役に立つ(5段階評価で4)を含めると9割以上から肯定的な評価を得ることができている.
また受講後の自施設体制整備では,勉強会やシミュレーションの実施,マニュアル作成,トラウマコールや大量輸血プロトコールの導入,MCIを含む災害対応計画への参画など様々な取り組みが行われるなど,医師看護師ペアで研修会に参加することにより院内多方面への働きかけが行われており,外傷診療体制の整備に寄与していることがうかがわれる13).
【外傷外科チームTrauma Surgical Assistance Team(TSAT)】
東京オリンピック・パラリンピック大会での医療体制整備を念頭に開始された上記研修であったが,本大会開催時に研修修了者が実際に招集され活動するには至らず,大会終了後も具体的な活用策は明確ではなかった.そのような中で元首相に対する銃撃事案が発生しテロによる外傷への対応の必要性が改めて浮き彫りにされ,さらに2023年に開催されるG7広島サミットでの要人対応も想定された.このような状況に対し,日本外科学会外傷外科医養成研修実施委員会では本研修修了者からなる外傷外科チームを編成し, 様々なイベントや災害発生時に派遣する体制を構築することとした.発足にあたり外傷外科チームの名称をTrauma Surgical Assistant Team (TSAT)とし,同研修修了者のうち希望するものをTSAT隊員として登録. TSAT は同一医療機関の医師1名,看護師1名をもって1隊とし,複数隊からなるチームを派遣する.TSAT 事務局は日本外科学会内に設置し,要請の内容によっては緊急性や秘匿性があることを考慮した体制となっている.派遣要請に対しTSAT事務局は隊員の選定と調整,派遣中の支援等を行い,活動終了後は理事会に対し活動報告を行い承認される(図3)14).
TSATの活動内容は,大規模イベントやマスギャザリング等に対する派遣もしくは待機,災害時の緊急派遣要請への応需,患者受け入れ施設の診療支援,イベント開催地域近隣にあるTSAT保有医療機関に対する別地域からのTSAT支援派遣等が考えられる.
一方「G7広島サミット救急・災害医療体制確保事業」の実施団体となった日本臨床救急医学会には日常の外傷診療体制を維持しつつ,首脳等に対する高度な外傷診療体制を確保することが求められた.具体的には1)ダメージコントロール等の超緊急手術が可能な野外手術ユニット (field operation system: FOS)を会議場近くに展開,2)首脳等受入れ医療機関の外傷診療能力の強化,の2点を行うこととなった.前者については2019年の伊勢志摩サミットと同様に防衛省の協力のもとFOSに複数の救命救急センターから経験豊富なAcute Care Surgeonを中心とした重症外傷診療チームが派遣された.そして後者に対しては診療のみならず院内体制整備の支援が可能な外傷外科医等養成研修の修了者が適任と考えられた.そして広島市内の2施設から日本臨床救急医学会に対し支援依頼があったことを受け,同学会よりTSAT事務局に対し派遣要請が行われ,初のTSAT派遣が実施された15).
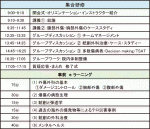

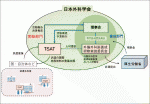
IV.G7サミットにおけるTSATの活動
依頼のあった両施設は県内の基幹病院として先進的な外科治療が提供されている一方,銃創や爆傷に対する外科治療の経験がほとんどないことからTSAT依頼の判断となった.派遣に当たっては,派遣先でのTSATチームを統括する統括医師を指定し,派遣先医療機関と事前準備を進めながら緊急時の受け入れと手術ができる体制を構築した(図4).筆者は統括医師として会期40日前からメールでの情報交換やオンラインの打ち合わせを実施し意思疎通をはかるとともに,TSATから病院に外傷診療体制やMCI・NBCテロ対応等に関する事項(病院前の連絡体制,各種院内設備,輸血体制,初療室・手術室・ICUの対応状況等)を確認,回答内容から事前に追加準備と調整が必要な項目(「準備血」と「外来での手術実施」等)を共有した.TSAT側からは隊員の顔写真つきプロフィールシートを提供し受け入れが円滑に行えるよう配慮した.そして手術に関しては原則として病院側が執刀しTSATはそのサポートを行うこと,時間外等で病院医師が間に合わない場合や並列手術の際にはTSATが執刀し病院側に引き継ぐ形とした.
現地での活動6日間を前後半に分け各施設に4チームが交代で派遣され活動,日中は常時2チームが待機し,夜間は1チームが施設内に当直する体制とした.
現地到着後は病院各部署との顔合わせ,部署配置(救命センター病棟,初療室,CT室,アンギオ室,手術室,ヘリポート,当直室等)と患者動線の確認を行うとともに,要人受け入れシミュレーションを行い初療から手術,そしてICU入室までの動きを具体的に調整した.また病院医療対策本部ミーティングへの参加,FOSとTSATをつなぐビデオ専用回線ネットワークによるミーティングにより情報と活動方針の共有を図った.また当直帯に救急搬送された腹部外傷の緊急手術にTSAT隊員が立ち会う場面があった.またTSAT 隊員から病院の若手医師に対し2回にわたり外傷診療に関する講義を行う機会もいただき活発な意見交換を行うこともできた.
派遣期間中に実際の要人受け入れはなかったものの,万一発生した場合にも相応の医療対応は可能と考えられた.郵便局に爆弾を仕掛けたという犯行声明が出され一時MCIの発生リスクが高まった事案や,某国大統領の急遽出席による不測の事態への対応強化など改めてTSATの意義を認識することとなった.
今回受け入れ施設の全面的な協力により TSATによる初の活動を成功裡に終えることができた.受け入れ側からも「VIP外傷やMCI対応への精神的な負担が軽減された」というコメントもいただいた.今後に向けては十分な準備期間の確保,受け入れ施設側に重症外傷診療に必要とされる各種基準値(輸血開始までの所要時間,執刀医が接触するまでの所要時間,手術開始までの所要時間など)を示すことでの体制整備促進,受け入れが予想される施設への外傷外科医等養成研修受講枠の優先的・計画的設定,各外科との十分なすり合わせなどが必要と考えられた.TSATについても現在の外傷外科医等養成研修では支援活動に関する項目はないため,TSATとしての研修プログラム(活動目的や活動内容の理解と習得,支援シミュレーション等)が必要である16)
17).
今回日本外科学会が中心となりTSATの派遣という新たなシステムの運用が開始された.国家的行事や大規模災害における重症外傷診療の支援提供を担うTSATの中心的メンバーとしてAcute Care Surgeonの活躍が期待される.
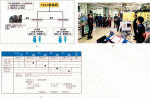
V.おわりに(Acute Care Surgeryにおける災害・MCI対応の将来)
Acute Care Surgery は, これまで外傷外科・救急外科・外科的集中治療を三つの柱として提唱されてきた18).近年は本特集でも触れられている術後合併症に対する集中治療やIVR治療,手術治療を担う surgical rescue が四つ目の柱となっている(米国では定時の一般外科手術elective general surgeryを加えた五つの柱で示されることもある)19).これらに加え,今回解説した災害・MCIでは外傷患者,とりわけ銃創,切創,爆傷など重篤かつ早期の介入が必要となる症例が多数発生することから,これをAcute Care Surgeryの担う領域とすることは極めて妥当でありかつ社会的にも期待されるところである.そしてこれに積極的に応えることはその意義からもAcute Care Surgeon の職域とidentityを確立するうえでも極めて重要と考える(図5).
その一方で災害・MCI対応を新たな柱とするには教育・研修体制の確立が必要である.現時点では外傷外科医等養成研修以外に外科の視点から災害対応を学ぶ機会はない.米国外科学会では2010年より災害医療を学ぶためのDisaster Management and Emergency Preparedness Course(DMEP)を開始,会員に対し「研修コースの受講→自施設の災害対策委員会への参加→自治体レベルの災害対策委員会への貢献→救援活動への積極的参加」という段階的なアプローチを示している.今後わが国でもこのような取り組みを検討することが必要である.
日本外科学会による外傷外科医等養成研修と今回のTSAT発足はDMATでは対応しきれないテロ等によるMCI対応への画期的な一歩となった.また,日本外科学会にとっても実働部隊となるTSATを有したことで災害時に公器としての学会使命を果たすことも可能となった.
一方外科専門医2万人に対しACS認定外科医はその1% 200名という現状にあっては,大規模災害では外科医全体の関わりが不可欠となる20).外科医に対し広くACS領域への関心を喚起するような取り組みや災害医医療を学ぶ機会の提供(米国ではオンラインのe-DMEPコースを開始)を行うとともに,災害時に外科医とAcute Care Surgeonが協調して対応できる体制づくりが求められる.
謝辞
今回TSATを受け入れていただいた広島大学病院,広島県立広島病院の関係者皆様に深く感謝申し上げます.
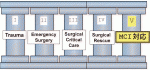
利益相反:なし
文献
1) Committee on Trauma, American College of Surgeons: Statement on disaster and mass casualty management. J Am Coll Surg, 197: 855-856, 2003.
2) Disaster Management and Emergency Preparedness. cited 1 Jan 2024. https://www.facs.org/quality-programs/trauma/education/disaster- management-and-emergency-preparedness/
3) Frykberg ER : Disaster and mass casualty management. A commentary on the American College of Surgeons position statement. J Am Coll Surg, 197: 857-859, 2003.
4) Frykberg ER , Hirshberg A : Surgeons and disasters. New challenges, new opportunities. Scand J Surg, 94: 257-258, 2005.
5) Ciraulo DL , Barie PB , Briggs SM , et al.: An update on the surgeon’s scope and depth of practice to all hazards emergency response. J Trauma, 60: 1267-1274, 2006.
6) Remick KN , Shackelford S , Oh JS , et al.: Surgeon preparedness for mass casualty events: Adapting essential military surgical lessons for the home front. Disaster Med, 11: 77-87, 2016.
7) Russo RM , Galante JM , Jacoby RC , et al.: Mass casualty disasters: who should run the show? Emerg Med, 48: 685-692, 2015.
8) 下条 芳秀 , 藏本 俊輔 , 室野井 智博 ,他:災害医療における Acute Care Surgeon の役割.外傷診療の延長線上に災害医療がある.Jpn J Acute Care Surg, 8: 227-231, 2018.
9) 益子 一樹 , 松本 尚 , 安松 比呂志 ,他: 成熟した Acute Care Surgery team が担う外科的危機管理部門としての機能.Jpn J Acute Care Surg, 13: 162-167, 2023.
10) 岡田 一郎 , 井上 和成 , 関 聡志 : 災害医療におけるacute care surgeon の役割とその育成.高度技能医および外傷リーダーとしての役割を中心に.Jpn J Acute Care Surg, 13: 157-161, 2023.
11) 渡部 広明 , 比良 英司 , 中尾 彰太 ,他:外科専門医のための外傷外科手術 off-the-job training(OFF-JT).5.Surgical Strategy and Treatment for Trauma(SSTT)コース.日外会誌,118(5): 527-531, 2017.
12) 松島 一英 : 外科専門医のための外傷外科手術 off-the-job training(OFF-JT) 4.Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma(ASSET)コース.日外会誌,118(5): 521-526,2017.
13) 森下 幸治 , 大友 康裕 , 庄古 知久 ,他:日本外科学会厚生労働省外傷外科医養成事業における院内体制調査報告書の分析. 2024年1月1日. http://2020ac.com/documents/ac/06/1/1/ 2020AC_JSS_厚生労働省
14) 渡部 広明 , 比良 英司 , 井上 潤一 ,他: TSAT設立とG7広島サミットでの対応と今後.Trauma Surgical Assistant Team(TSAT)の設立と今後の展望.Jpn J Acute Care Surg, 13 (Suppl): 61, 2023.
15) 溝端 康光 , 内田 健一郎 , 渡部 広明 ,他:TSAT 設立とG7 広島サミットでの対応と今後.TSATの有効活用について.G7広島サミットでのTSAT派遣の経験から. Jpn J Acute Care Surg, 13 (Suppl) :63, 2023.
16) 大友 康裕 , 伊澤 祥光 , 福間 博 ,他:TSAT 設立とG7 広島サミットでの対応と今後. 広島大学病院での支援実施と課題.Jpn J Acute Care Surg, 13 (Suppl): 62, 2023.
17) 井上 潤一 , 日高 国 , 林田 和之 ,他:TSAT 設立とG7 広島サミットでの対応と今後. 広島県立病院における活動,その成果と課題. Jpn J Acute Care Surg, 13 (Suppl): 62, 2023.
18) Moore EE : Acute care surgery: the safety net hospital model. Surgery, 141: 297-298, 2007.
19) Griepentrong JE , Lewis AJ , Rosengart MR , et al.: Acute Care Surger. InFeliciano DV, Mattox KL, Moore EE(eds):Trauma, 9th ed. McGraw Hill, New York, 129-134, 2021.
20) 飯坂 正義 , 中原 修 , 辻 顕 : 過去から未来に繋げる災害医療と外科医の役割 3.大規模災害時における外科医の役割と今後の課題について.熊本地震,令和2年7月豪雨を経験して. 日外会誌,124(1): 134-136, 2023.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。