日外会誌. 125(3): 199-206, 2024
特集
Acute Care Surgeon―その活躍の場―
2.病院前救急医療におけるAcute care surgeonsの活動と今後の展望
|
公立豊岡病院 但馬救命救急センター 永嶋 太 |
米国において新たな外科領域として登場したAcute Care Surgery(ACS)は,本邦においても,その重要性が高まり,外科専門医に新たな活躍の場を提供している.急性期の患者ケアに特化した専門性の高い医療を提供する目的で,病院内での活動に加えて,病院前医療の領域へも活動範囲が拡大している.病院前医療では,ドクターヘリやドクターカーを用いた早期医療介入が重要な役割を果たしており,そこにACS医が関与することで,ダメージコントロール戦略を病院前から開始し,心停止を回避するための蘇生的開胸術を含む蘇生的手術を迅速かつ的確に施行可能となる.これにより,院内でのdamage control surgeryに繋げ,一連の戦略をシームレスに実行することが可能である.さらに,病院前における重複事案,特殊事案,多数傷病者事案においても,ACS医は救急医と共にcommand and control,トリアージ,搬送を行うことにより,救命率のさらなる向上が期待される.これらを通じて,有事の際に対応可能なACS医となりうる.
キーワード
Acute Care Surgery, ドクターヘリ, ドクターカー, 病院前救急診療, ダメージコントロール戦略
I.はじめに
米国において新たな外科領域として登場したAcute Care Surgery(ACS)は,外傷外科,救急外科,集中治療を包含するもので,本邦でもその重要性が認識され,外科専門医の新たな活躍の場となっている.病院内での活動に留まらず,その活動範囲は病院前医療にも広がっている.
本稿では,ドクターヘリ(Doctor Helicopter: Dr Heli)やドクターカー(Doctor Car: Dr Car)を用いた病院前医療におけるACSの実際とその将来展望について述べる.
II.病院前救急診療の目的とその重要性
近年,ACSは顕著な進展を遂げ,内因・外因を問わず,重症患者の救命が多数報告されている.しかし,外傷症例では,「防ぎ得た外傷死」が依然として発生している.これらの中には,病院前の早期医療介入によって救われたと考えられる症例も含まれている.これに対応するため,医療スタッフは,病院前に出て診療を行うようになった. Dr HeliやDr Carが多くの施設で導入され,救急隊による救護活動とともに本邦の救急医療を支える重要な役割を果たしている.
病院前救急診療は,早期医療介入ばかりでなく,適切な蘇生および安定化処置,搬送先病院の適切な選定,搬送時間の短縮,搬送中の継続診療,および病院到着後の迅速な根本的治療開始など,幅広い目的で施行されている.
1993年にRotondoによって報告された「ダメージコントロール(Damage Control: DC)」は,重症外傷の生理学的機能破綻の改善に焦点を当てたものであり1),現在では外傷治療に留まらず,重症内因性疾患への応用も進んでいる2).その概念は,病院前の初期診療から蘇生,手術やIVR,集中治療に至るまで,外傷治療の全過程に渡って適応されている3)
~
6).DCは,DC1:迅速な出血の制御と汚染の回避に主眼をおいた蘇生的手術,DC2:生理学的異常の改善を目指した集中治療,DC3:計画的根治的手術(planned definitive surgery)の3段階に大別されている1).その後,Johnsonは,DC0(ground zero)として病院前救急診療から救急初療室までの治療の重要性を強調し7),DC4:根治的治療後のopen abdomenに対する腹壁再建を加え,DCは5段階であるとした.DC0では,「The right patients to the right place in the right time」という原則に基づき,適切な初期診療および蘇生を含む安定化処置を行い,以前は病院搬入後から始まっていたDamage control resuscitation(DCR)も病院前から開始することが含まれている.
病院前救急診療のスタッフの多くは,救急医や救急看護師であるが,ACS医が対応している施設もある.実際,病院内において,DC1〜DC4までを日常から実践しているACS医は,病院前救急診療およびDC0においても,重要な役割を果たしており,ACS医の介入が求められる症例も多く存在する.
III.病院前救急診療の実際とACS医の活動と役割
傷病者が発生し,消防に119番通報されると,消防司令が救急車を現場に出動させる.そして,Dr HeliやDr Carは,①消防覚知時,②救急隊の患者接触後に要請される.特に①の場合には,キーワードに基づいて要請される(図1)ため,より早期の医療介入が可能である.しかし,オーバーインディケーションを許容した要請方式であるため,キャンセルされる場合もある.
Dr Heli/Carスタッフは,ランデブーポイント(Rendezvous Point:RP)またはドッキングポイント(Docking Point:DP)で患者と接触する(図2).Dr Heliの場合,RPに救急車が未到着の際は,消防支援車に乗り込み,現場に直接向かうこともある(図3).Dr Carでは,直接現場に向かい,患者と接触する事案もある.
RP/DPで患者接触時,救急車内で救急隊による救命処置と患者状況の情報収集を行いながら,初期診療と必要な蘇生処置を開始する.病院前救急診療の特徴として,根本的治療やCT・Xpによる画像検査が困難であり,診療環境や時間に制限がある点が挙げられる.しかし,心停止を回避する蘇生処置は可能であり,緊急止血術や大量輸血のプレホスピタルオーダー,トラウマコードなどを発動することで,院内対応の準備が早期に可能となる.これにより,患者搬入後の迅速な緊急止血術と大量輸血が可能となる.当センターにおける過去10年間の,DC戦略で対応した症例のDr Heli群,Dr Car群,救急車単独群の比較研究では,搬入から手術開始までの時間は,それぞれ2.3分,2.0分,21.5分(p<0.01),輸血開始時間が6.4分,6.6分,16.2分(p<0.01)と有意にDr Heli/Car群が短かった(表1).
重症外傷の場合,RP/DPでの患者接触後,患者の緊急度と搬送距離・時間を考慮し,蘇生処置や安定化処置を救急車内や現場でどこまで施行するか決定する.Dr Heli内でも可能な処置は,できるだけDr Heli内に収容し搬送しながら施行する.院内における根本的治療の早期開始を目指し,現場滞在時間を最小限に抑えるため,可能な限り搬送しながらの処置や検査が有効である.Dr Heliの機内は非常に狭く,患者へのアクセスが限られるが,適切なトレーニングと経験により,気管挿管,外科的気道確保,胸腔ドレーン挿入,finger thoracostomy,蘇生的開胸術(resuscitative thoracotomy: RT),動脈アクセス確保,輸液路確保,薬剤投与,FAST/EFASTなどは,搬送中に施行可能である.特に,心停止を回避するために病院前のRTを含む外科処置が必要な場面において,ACS医の役割と必要度が増す.ACS医は,病院前RT後,院内に搬送された後も,そのまま一連の流れで蘇生的手術(DC1)に入ることによりシームレスな外傷外科手術が行える.この点が,病院前救急診療におけるACSの最大の意義であると考えられる.
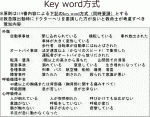
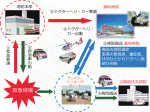
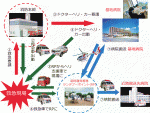
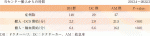
IV.病院前救急診療におけるcommand and controlとACS医の活動
Dr Heli/Carを積極的に活用している地域では,重複要請事案,特殊現場事案,多数傷病者事案などに対応する場面がある.
1)重複要請事案への対応
出動途中で重複要請がある場合,要請内容と距離・到着時間を考慮し,リーダー医師が対応の戦略を練る.次事案に対して,まずはDr Carを出動させ,早期医療介入を図り,現事案をDr Heliで対応(搬送終了)後,Dr Carスタッフが介入した次事案に対し,ホットローディング(エンジンカットせず)で向かう.新設RPでDr Carスタッフから引き継ぎ,Dr Heliで搬送する.または,Dr Heliスタッフのうち医師1名を現事案のRPでドロップし,残りのスタッフで次事案に向かう.ドロップされた医師はRPに到着する救急車内で初期診療を開始し,診療しながら搬送先病院に向けて出発する.必要時,前事案対応後のDr Heliを再要請し,新RPを設定し,そこでDr Heliに引き継ぎ,搬送する.
上記のように,重複事案に対しては, Dr Carとの連携,ホットローディング対応,ドクタードロップ対応といった決断が必要である.日常よりこういった決断をすることにより病院前におけるcommand and controlの基本を実践・経験することが可能である.また,最初の事案が重症外傷症例の場合には,初期診療と蘇生処置を行い,トラウマコードや大量輸血,緊急手術などのプレホスピタルオーダーを発動し,必要に応じて病院前RTを行い搬送する.その後,ACS医はDr Heliの担当を,別のスタッフに交代し,ACS医はそのままその重症外傷の院内での診療/手術に入り,Dr HeliはホットローディングでDr Car先行事案に向かう.次事案が重症外傷であれば,現事案に対して救急医をドロップで対応し,ACS医はフライトナースとともに外傷事案に向かう.ACS医は,搬送後もそのまま院内でも,その重症外傷症例の診療に加わり,Dr Heli担当は交代で別の医師がホットローディングでドクタードロップ事案に向かい対応する.
このようにACS医は,重症外傷に対する病院前のDC0から院内におけるDC1までシームレスに関わるばかりでなく,重複ミッションのcommand and controlを施行することで,病院前診療において,災害医療で必要な要素も実践することが可能である.
2)特殊現場での対応
病院前救急診療では,工事現場や山岳・海難事案など特殊現場での対応が必要な場面もある.Dr Heliでの対応では,RPから消防支援車に乗り込み,現場に向かう.山岳・海難事案は,Dr Heliスタッフは自己および他のスタッフの安全装備を確実にし,消防隊の先導で現場に進入する.現場へ進入するかどうかは,安全面を最優先に考慮し,消防指揮隊長との交渉を通じて決定する.安全面から,患者との接触は医師1名に限られることもある.患者接触後,迅速に初期診療と蘇生処置を施行する.安全面から医療スタッフの人員が限られる場合,救急隊と適切に連携し,救出・搬送のためのパッケージングを行う.特殊現場では,患者接触から搬送まで時間を要するため,症例によっては現場で外科的治療をある程度完結しなければならない場面がある.そのような状況では,ACS医の役割が増大する.場所や医療資機材の制限,長時間の病院搬送を考慮して,RTを含む心停止回避のための蘇生処置も的確に行う必要がある.そういった観点からもACS医が病院前に出る価値は大いにあると思われる.
パッケージングしながら,病院に搬送する手段を検討する.RPまで搬送に時間がかかる場合,消防防災ヘリでの搬送を第一に考える.患者を消防防災ヘリに収容後,医師も吊り上げにより搭乗することが可能な場合もあるが,稀であるため,患者の吊り上げ開始までに蘇生処置を完了していなければならない.消防防災ヘリに患者収容後,搬送距離と患者の状態に応じて,そのまま医師同乗なく防災ヘリで搬送するか,RPでDr Heliスタッフが引き継ぎ,Dr Heliで搬送する.その際には,患者接触しなかった別のDr HeliスタッフをRPに待機もしくは移動させておく必要がある.患者が不安定な場合は後者の方法で対応する.
3)多数傷病者事案の対応
多数傷病者への対応も病院前救急診療では重要である.車の複数台事故やバス,列車事故などが多い.Dr Heliが要請された場合,医師を1名増員して出動する.傷病者が4名以上の場合,Dr CarまたはDMAT Carを同時出動させる.発生場所に応じて近隣のDr Heliも要請する. Dr HeliはRPに到着後,消防支援車で消防の現場指揮所へ向かう.現場で傷病者の救出が完了している場合,RPが搬送拠点場所となる.消防の現場指揮隊長と連携し,Dr Heliリーダー医師がcommand and controlを行う.現場救護所では,残りの医療スタッフがトリアージと治療を行い,その結果に応じて,リーダー医師が搬送の優先順位と搬送手段を決定する.特に緊急度が高く,初期治療の反応が悪い赤の傷病者の搬送を最優先して決定する.FAST陽性のショック症例は緊急度が特に高く,ACS医が病院前初期診療と蘇生処置を行い,緊急手術と大量輸血のプレホスピタルオーダーを行いつつ搬送する.搬送前または搬送中,切迫心停止となれば,病院前RTを施行し搬送する.病院到着後はダイレクトに手術室に搬入させ,緊急手術を施行する.
現在,国,県,地域単位で大規模災害訓練が施行されているが,病院前救急診療を積極的に行う施設では,このような多数傷病者事案での実症例を通じてACS医として災害医療時の対応を経験している.日常から重症外傷や重症例の緊急手術や集中治療,surgical rescueを行っているACS医は,多数傷病者対応の実例でcommand and control,トリアージ,搬送および重症例のDC0からDC1に至る連続したシームレスな対応を行うことにより,有事の際には重要な役割を果たすことが期待されている.
V.ACS医が特に施行すべきDC0の項目
病院前救急診療におけるDC0からDC1で施行すべき項目を図4に示す.ACS医が特に求められる病院前診療の項目は,心停止を回避するための病院前RTとそれに続く一時的止血である.重症外傷患者に対して,心停止をいかに回避しつつ院内でのDC1に繋げるかが重要である.RTの適応は,外傷性心停止に対する蘇生手技として考えられがちであるが,本来の目的は心停止を回避するための蘇生的手技である.外傷の場合,一度心停止に至ると死亡率が急激に上昇するため,重篤なショックの場合,病院前の現場,救急車内,Dr Heli内で病院前RTを迅速かつ的確に施行し,心停止させずに搬送することが重要である.これが病院前での重症外傷診療の最も重要なポイントである.また,病院前で接触時には,ショック状態でない場合でも,搬送中に急激にショック状態となり,心停止が切迫する症例がある.これに対しても, RTを施行し,大動脈遮断を迅速かつ的確に施行しなければならない.また,心タンポナーデや肺裂傷,大血管損傷などといった重症胸部外傷を認める場合には,心嚢開放,心損傷の一時止血,肺門部クランプ,胸壁の一時止血,血管遮断や一時的シャントなどといった蘇生処置も,病院前でだからこそ必要であり,ACS医はトレーニングと経験を積み,施行できなければならない.
当センターにおいて過去10年間で病院前RTを施行した約250症例のうち,施行者の内訳は,ACS医:救急医=55%:45%であった.そのうち,不完全RT(不完全な大動脈遮断,一時止血が不十分など)の割合は,ACS医:救急医=1.3%:23%(p<0.01)であった.心停止症例に対するRTは救急医でも施行可能かもしれないが,心停止が切迫している緊急度の高い状況や重症胸部外傷を合併する症例に対して,病院前RTを確実に施行できるのは,トレーニングを受け,経験のあるACS医である.
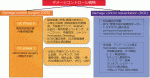
VI.おわりに~将来の展望~
重症患者に対して,病院前での早期医療介入を実現するためには,消防による覚知同時要請と,それを支えるメディカルコントロール体制の構築が必要である.このような重症患者には,救急隊が現場到着後にDr Heli/Dr Carを要請しても,早期医療介入は実現しない.キーワード方式による覚知同時要請が必要である.また,早期医療介入が実現されても,医療スタッフがDC0を確実に施行し,RTを含む心停止回避蘇生処置が施行できなければ,救命率のさらなる向上は期待できない.
本邦では,交通外傷の減少に伴い,重症外傷例も相対的に減少している.しかし,大規模イベント,要人によるサミットや会議などでのテロ災害,局地災害や多重事故などが発生する可能性があるため,それらに備える必要がある.そのために, ACS医が救急医や救急看護師と共に,日常的に病院前での活動を行い,ACS医としての専門性を活かした病院前診療とcommand and controlの確立,トリアージ,搬送を,実臨床で行い,経験値を高めることが求められる.これを実践することにより,有事の際に対応可能なACS医になれると考えられる.これからは,ACS医の活動・活躍の場を病院前にさらに拡げるべきである.
利益相反:なし
文献
1) Rotondo MF , Schwab CW , McGonigal MD , et al.: “Damage control” I an approach for improved survival in exsanguinating penetrating abdominal injury. J Trauma, 35 : 375-382 i discussion 382-373, 1993.
2) Stawicki SP , Brooks A , Bilski T , et al.: The concept of damage control: extending the paradigm to emergency general surgery. Injury, 39: 93-101, 2008.
3) Tourtier J-P , Palmier B , Tazarourte K , et al.: The concept of damage control:Extending the paradigm in the prehospital setting. Ann Fr Anesth Reanim, 32: 520-526,2013.
4) Holcomb J , Jenkins D , Rhee P , et al.: Damage Control Resuscitation: Directly Addressing the Early Coagulopathy of Trauma. J Trauma, 62: 307-310, 2007.
5) Sugeir S , Grunstein I , Tobin JM : Damage Control Anesthesia. In: Duchesne J, Inaba K, Khan M, ed. Damage Control in Trauma Care. Cham: Springer, 193-207, 2018.DOI: 10.1007/978-3-319-72607-6_16.
6) Matsumoto J , Lohman BD , Morimoto K , et al.: Damage control interventional radiology (DCIR) in prompt and rapid endovascular strategies in trauma occasions (PRESTO): A new paradigm. Diagn Interv Imaging, 96: 687-691, 2015.
7) Johnson J , Gracias V , Schwab W , et al.: Evolution in Damage Control for Exsanguinating Penetrating Abdominal Injury. J Trauma, 51: 261-271, 2001.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。