日外会誌. 125(5): 444-448, 2024
会員のための企画
小児固形腫瘍の現在と未来
|
国立成育医療研究センター 外科・腫瘍外科 米田 光宏 |
本邦における小児固形腫瘍手術は年間500件未満とその数は極めて少ない.さらに疾患の種類や腫瘍発生部位は多岐に及んでおり,定型的な手術を繰り返し経験することは困難である.したがって,ひとりの外科医が小児固形腫瘍手術に習熟するにはハイボリュームセンターで一定期間トレーニングを積む必要がある.また,悪性腫瘍においては成人がんよりも圧倒的に化学療法や放射線治療の効果が高く,外科治療の役割は相対的に低くなる.しかしながら,集学的治療の中で適切なタイミングで適切な外科治療を組み入れること,他領域や成人がんに特化した専門的外科治療をコーディネートすることなど小児固形腫瘍を担当する外科医には様々な専門的能力が求められている.
小児がんを理解して,児の長い将来を見据えた外科治療を遂行できる外科医をどうやって育成するか?希少疾患の治療研究体制・診療体制はどうあるべきかなどを考察し,若手外科医に向けた小児固形腫瘍の現状と未来について私見を中心にのべてみたい.
キーワード
小児固形腫瘍, 小児がん, 集学的治療, 外科治療, 長期フォローアップ
I.はじめに
駆け出しの小児外科医であったある日,大学病院の小児外科に進行神経芽腫の患児が紹介された.切除不能と考えた私は,小児科腫瘍グループに相談に行き,まず化学療法を開始する算段をした.しかしながら小児外科の症例検討会で「外科に紹介されたんやからまず手術やろ!」と叱責されたことを覚えている.患児の治療(運命)は「最初に何科に紹介されるか」で決まっていたのである.当時は日本小児外科学会でも盛んに化学療法についてディスカッションが行われ,小児がんの基礎研究に携わる小児外科医も多く存在した(かくいう私もそのひとりである).それから30年以上経った今,集学的治療の進歩により小児がんの治療成績は急速に改善し,今では多くの疾患で8割以上が病気を克服する時代になった1).治療の役割分担が進むとともに化学療法を行う小児外科医はほとんどいなくなった.小児がんの基礎研究に携わる外科医も少なくなり,小児がんを生業とする小児外科医は絶滅危惧腫とさえ呼ばれるようになった.
しかしながら,小児がんの集学的治療の中で外科医には重要な使命がある.腫瘍摘出という最重要のミッションに加え,腫瘍生検,中心静脈カテーテル挿入,oncologic emergencyに対する外科治療など様々なタスクが求められる.小児がんの特性を十分理解した上で,適切な時期に適切な外科治療を行うことができる外科医が必須である.
まだまだ「小児がん,小児固形腫瘍を専門とする外科医は必要」というメッセージを若手外科医に送る絶好の機会と捉えて,本稿を執筆させていただく次第である.
II.小児固形腫瘍の多様性と希少性
小児外科で手術を受ける患児は体重500g前後の超低出生体重児から50kgを超えるAYA世代のこともある.手術部位は,腹部や胸部のみならず頸部,軟部組織におよぶこともある.
同様に小児固形腫瘍にも多様性と希少性という問題がある.本邦で小児がんに罹患する児の数は年間2,500例前後とされる.成人がんの罹患数に比べると1%にも及ばない.小児がんの半数以上は血液腫瘍や脳腫瘍であることから,小児外科医が担当する固形腫瘍はさらに少なくなり年間500例以下と推定される.実際,2021年NCD annual reportによると,16歳未満の年間NCD登録例中専門領域で「小児外科」が選択されたのは46,625例であった.このうち悪性腫瘍根治術が275例,縦隔・後腹膜・仙骨前良性腫瘍摘出が152例で合計すると427例(0.92%)である2).
しかしながら厚生労働省2023人口動態年報によると1~19歳までの年齢階級別死因では,悪性新生物が常に1位から3位の中に含まれており,小児の病死原因としては最もメジャーな疾患である(表1).しかも疾患は多岐に及んでおり,疾患毎の発症数はさらに少なくなる.小児外科医が扱う小児悪性固形腫瘍で最も頻度が高いのは神経芽腫であるが,本邦における年間新規発症は150例程度である.好発年齢である0~4歳の年齢層で10万人あたり約2人の発症頻度となり10万人あたり6例未満と定義される希少がんの範疇に入る.神経芽腫以外の固形腫瘍はさらに希で,数年に一度しか経験しない専門領域の外科治療を要する患児を担当することもあり,呼吸器外科・肝胆膵外科・消化管外科・移植外科・整形外科・泌尿器科・婦人科等他領域の外科医と協働しながら外科治療をコーディネートすることが求められる.反面,小児がんは成人がんに比し化学療法や放射線治療の効果が高い腫瘍が多いことから,集学的治療の中で外科療法をどのように組み入れるかが治療戦略の重要なポイントとなる.小児固形腫瘍を担当する外科医には,集学的治療全体を把握し,それぞれの腫瘍の特徴を理解した上で外科治療戦略を立て実行する能力が求められる.
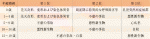
III.患児の将来を見据えた小児固形腫瘍の外科治療
本邦での新規発症数は約2,500例でその80%が治癒することから,毎年約2,000人の小児がんサバイバーが育っていくことになる.彼らが治療後の長い人生を歩んでいくために,晩期合併症を最小限に抑える治療開発が求められる.外科治療についても例外ではない.根治を目指して必要な腫瘍切除は行わなければいけないが,本当に全摘を目指す手術が予後を改善するのか?臓器合併切除は本当に必要なのか?化学療法や放射線治療により切除を免れることができないか?常にこのような確認を行いながら外科療法を決定していくことが必要である.
例えば神経芽腫は極めて多様性のある小児がんである.低リスク患児の中には,化学療法も外科治療も必要とせず自然退縮する腫瘍があることが知られている.反面,高リスク神経芽腫は全身転移のコントロールが極めて難しく,最新の治療手段を駆使しても未だに2人に1人しか救命できない状態である3).したがって正確なリスク評価を行って適切な治療を選択することが極めて重要である.
外科治療に特化して考えてみると,神経芽腫はしばしば腎血管を巻き込んで発育するため,拡大手術が推奨されていた時代には,腎合併切除を行い,さらに腹部大動脈,下大静脈,腎動静脈周囲のリンパ節を徹底的に郭清していた.再発する可能性が高い児にとって片腎を失うことは再発後化学療法の選択肢を狭めることになる.その後高リスク神経芽腫の再発部位は局所よりも遠隔転移部位に多いことが明らかとなり,拡大手術に明確な優位性がなく,可能な限り腎温存に努めることが推奨されるようになった.特に本邦では遠隔転移巣に対する全身治療を優先し,手術による化学療法の中断を避け局所治療を最後に行うという日本独自のdelayed local treatmentが標準治療となっている4).
これまで行ってきた治療がどのような晩期合併症をもたらすかの評価も重要で,長期フォローアップを行うことは必須である.北米の小児がん臨床研究グループChildren’s Oncology Group(COG)は長期フォローアップガイドラインを作成し,ウェブサイトに公開している.「Surgery」の章だけでも42ページある.例えば開腹手術後には,癒着,腸閉塞が晩期合併症として挙げられており,1年ごとに腹痛,腹部膨満,嘔吐,便秘の病歴聴取と腹部診察が推奨されている.腎摘後であれば,蛋白尿,腎不全,高血圧,過剰濾過が挙げられており,1年ごとの身体測定,血圧測定,血液・尿検査が推奨されている5).近代的な小児がん治療が行われるようになって半世紀も経過していないことを考えると,今後これら長期フォローアップのデータをフィードバックして現在の治療を見直すことが重要である.
また,近年小児においても妊孕性温存が注目されるようになった.アルキル化剤をはじめとした妊孕性に負に働く薬剤や放射線治療の影響に加え,性腺・生殖器に影響する外科治療によって妊孕性を失う例も少なくない.2017年に日本癌治療学会が「小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」を作成した6).その中で小児がん患者に関しては,妊孕性温存療法として精子・卵子の凍結保存,思春期前の女児には卵巣組織凍結保存も推奨されている.卵巣組織凍結保存は0歳の女児に対しても行うことが可能であるが,保険収載されておらず限定された研究機関でのみ行われている.自身で判断できない小児の妊孕性温存については長期の組織保存の技術的問題,費用面の問題解決や児が成長したときに適切に説明を行い心理面をサポートする環境を整えることが求められる.
IV.小児固形腫瘍を含む小児がん治療・研究体制
「はじめに」で述べたように個々の施設(科)で独自の治療を行っている状態では,希少疾患である小児がんの治療研究の進歩は遅々としたものであったが,徐々に多施設共同研究の重要性が認識され治療研究組織が構築されるようになってきた.血液腫瘍は固形腫瘍に先んじて,1960年代後半に東京小児がん研究グループ(TCCSG)が発足,2003年には全国組織の日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)が結成された.固形腫瘍については,1989年に肝芽腫(JPLT)が最初に全国組織の疾患グループとして結成され,その後全国規模の疾患グループが結成されていき,最終的に2007年日本小児がん臨床試験共同機構(共同機構)としてまとまるようになった.希少疾患である小児がんをオールジャパンで疾患横断的にまとまって治療研究体制を構築することが求められ,2014年12月にJPLSGと共同機構がまとまって日本小児がん研究グループ(Japan Children’s Cancer Group:JCCG)が結成された.以降共通基盤を整備しながら,臨床研究を行って診断法や治療法の開発を行っている1).
診療体制については,成人がんと同じように小児がんにも拠点病院・連携病院が整備され,小児がん拠点病院は全国15施設が指定されている.拠点病院と連携して診療にあたる小児がん連携病院は2023年9月時点で総数143施設,うち標準治療が確立しているがん種について拠点病院と同等程度の医療が行える類型1に指定されているのは101施設である.年間500例未満の小児固形腫瘍手術数を考えると集約化は必須である.しかしながら,子どもが住み慣れた環境や学校,友達から遠く離れて治療を受けることには困難が生じる.両親の仕事の継続,きょうだいの転校を避けたい,などの理由から居住地を離れることは難しく,遠隔地で治療を受ける場合家族が離れ離れになることや経済的な負担など大きな問題がある.これらの問題を解決しない限り,強引に集約化を進めることは容易ではない.
V.小児固形腫瘍を担当する外科医の育成と国際協力
日本小児血液・がん学会では小児がん治療に精通した小児外科医を「小児がん認定外科医」として認定している.外科・小児外科専門医のいわゆる3階建てに相当する認定医制度で2024年4月現在129名が認定を受けている.小児外科専門医・指導医であれば充分ではないか?なぜこのようなマイナーな資格が必要なのか?とご指摘を受けることがある.小児がんを理解して集学的治療の中で適切な判断を下すためには,小児外科専門医・指導医資格を取得しただけでは充分とは言えず,さらに小児固形腫瘍に関する研鑽を積む必要があるとお答えしている.
小児がん認定外科医の主な申請要件を表2に示す.手術経験として「腫瘍摘出術を20例以上経験していること」という要件がある.「たった20例?」という疑問を持たれる方も多いであろう.しかしながらこの要件を満たすには小児がんのハイボリュームセンターで一定期間研修を積まないと達成できないのが現実である.
手術数が少ないことを克服する手段としてwebカンファレンスにおける手術症例の共有がある.JCCGでは中央画像診断が行われており,各施設から送られてきた臨床試験登録例の画像データを匿名化してクラウドにuploadし,全国の研究者がアクセスできるシステムを構築し,中央画像診断や治療方針のコンサルテーションに利用している.多施設の外科医が集まってコンサルテーション症例について画像データを共有しディスカッションすることが可能である.ベテランから若手までいろんな年代の外科医が参加することで,経験の伝承や知識の共有が行え,次世代の外科医の育成に効果を発揮することが期待される.
また,コロナ禍において海外とのwebカンファレンスが普及してきた.中央画像診断と同じシステムを利用する遠隔画像診断システムを利用して国際カンファレンスが行われている.私もカンボジアJapan Heartやベトナムのフエ中央病院との定期的なwebカンファレンスに参加し,低・中間所得国(LMIC)の小児がん治療の発展に協力している7).またLMICからの神経芽腫相談症例をディスカッションするGlobal Neuroblastoma Networkなど疾患別の国際カンファレンスが行われている.少子化の日本とは対照的にLMICの多くは小児人口の割合が高く,小児がん症例も多い.症例を共有することで日本の若手にとっても経験値が上がるメリットがある.日本小児外科学会では海外において指導医のもとで担当した手術を小児外科指導医の経験症例として算入できる制度を設けている.国際協力を推進することは,少子化の中の希少疾患の手術経験を増やすための一つの方策となり,LMIC側にとっても高い医療レベルの治療を受けられるメリットがある.今後このようなwin-winの関係が拡がることを期待する.
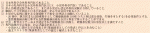
VI.おわりに
「こころ分子とみらいにおきてメスを構えるべし.」
小児固形腫瘍手術に臨むとき心の中で唱える座右の銘である.「小児がん外科治療」について語り合う同士である九州大学小児外科教授,田尻達郎先生との合作で,その原典は大阪大学外科の大先輩で熊本大学名誉教授,小川道雄先生のご著書8)にあった「こころ分子におきてメスを構えるべし」という言葉にある.患児を前にして,この子の腫瘍の病態をちゃんと理解しているか,長い将来を考えて正しい術式を選択しているか,計画した手術プランを遂行することができる自分・チームであるかを確かめてメスを構えることを忘れずにいたい.
利益相反:なし
文献
1) 堀部 敬三 :小児がん医療・研究の課題と展望.日小児血がん会誌,58(5):331-339,2021.
2) 日本小児外科学会NCD連絡委員会:National Clinical Database(小児外科領域)Annual Report 2021.日小外会誌,59(5):912-918,2023.
3) Yoneda A : Role of surgery in neuroblastoma. Pediatr Surg Int, 39(1): 177, 2023.
4) Yoneda A , Shichino H , Hishiki T , et al.: A nationwide phase II study of delayed local treatment for children with high-risk neuroblastoma:The Japan Children’s Cancer Group Neuroblastoma Committee Trial JN-H-11. Pediatr Blood Cancer:e30976, 2024.
5) Long-Term Follow-Up Guidelines for Survivors of Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancers Version 5.0, [cited 5 May 2024].Available from: http://www.survivorshipguidelines.org/pdf/2018/COG_LTFU_Guidelines_v5.pdf
6) 日本癌治療学会編:小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 2017年版.金原出版,東京,2017.
7) 七野 浩之 , 山中 純子 , 瓜生 英子 ,他:小児国際医療支援と遠隔医療 ベトナムの小児がん医療に対する国際医療支援の経緯と概要.映像情報Medical,49(3):56-61,2017.
8) 小川 道雄 :分子生物学とこれからの外科臨床.小川道雄,齋藤英昭(編),外科分子病態学,医学書院,東京,pp343-344,1999.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。