日外会誌. 125(1): 64-68, 2024
会員のための企画
臨床研修病院における外科医の働き方改革
|
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 消化器外科 寺嶋 宏明 |
医師に対する時間外・休日労働の上限規制と長時間労働医師に対する健康確保を規定した法律がいよいよ2024年4月より施行される.当院では,全医師における勤務実態の把握と時間外労働時間シミュレーションを行い,「全医師原則A水準」が達成可能と判断し,時間外労働時間削減に向けて,新勤怠管理システム導入・宿日直体制見直し(シフト制やフレックス制度の導入)・タスクシェア・シフト・時間外労務管理徹底化等の取り組みを行い,業務量の多い外科医にも達成可能な働き方改革を目指している.外科医に課せられた業務ミッションは膨大ではあるが,外科医の負担が少しでも軽減し,仕事に対するやりがいが向上する環境を作り上げることが必要である.
キーワード
働き方改革, 時間外労働上限規制, 追加的健康確保措置, 面接指導, タスクシェア・シフト
I.はじめに
長時間労働の是正による健康確保と,ワークライフバランスを考慮した多様性と柔軟性を許容する働き方の実現を目指す事は,医療の質と安全性の確保や将来の医療従事者の人材確保,ひいては地域の医療体制維持に直結する.医師に対する時間外・休日労働時間の上限規制と長時間労働医師に対する健康確保を規定した法律が,いよいよ2024年4月より施行される.医療機関は各々の医療実情に応じた働き方改革への対策を練り,“best answer”ではないにせよ,ほぼ形をなしていると思われる.
臨床研修医の教育を担う臨床研修病院における外科医の立場として,現在に至るまで取り組んできた働き方改革への対応・対策を,今後解決するべき課題を交えながら呈示する.
II.医師の時間外労働上限規制の概要
医師の働き方改革に関しては,厚生労働省のホームページに多くの情報が掲載されているが1),重要なポイントは以下の二つである(表1).
①時間外労働の上限規制
労働基準法上の特別条項付きの36協定を締結した場合,原則として年960時間以下/月100時間未満(以下,「A水準」)に制限されるので,医療機関は改めて36協定などの自己点検が必要となる.ただし,地域医療提供体制確保の観点からこの原則上限を超えざるをえない場合(地域医療確保暫定特例水準)や,一定の期間に集中的に技能向上の必要がある場合(集中的技能向上水準)は,都道府県知事が指定する機関においてのみ上限規制が緩和され,年1,860時間以下/月100時間未満の時間外労働が認められる.地域医療確保暫定特例水準には,他の医療機関に医師を派遣する医療機関(大学病院等)で,主たる勤務先の時間外労働は年960時間以内であるが,副業・兼業先の労働時間と通算すると960時間超えとなる「連携B水準」と,救急医療等を提供する医療機関での地域医療提供体制確保のための「B水準」がある.一方集中的技能向上水準には,臨床研修医・専攻医が研修プログラムに沿って修練をする際に適用される「C-1水準」と,医籍登録後の臨床従事6年目以降の医師が高度技能の修得研修する際に適用される「C-2水準」がある.これらの各水準は診療科もしくは医師個人単位に適用されるので,一人でもB水準以上適用の医師がいれば,医療機関として都道府県に指定申請をせねばならない.
②追加的健康確保措置の義務化
医師の健康確保のための新しいルールとして,追加的健康確保措置①(28時間までの連続勤務時間制限・9時間以上の勤務間インターバル確保・代償休息付与等)と追加的健康確保措置②(時間外労働が月100時間以上の医師に対する面接指導,その結果を踏まえた就業上の措置等)が義務化される.なお,追加的健康確保措置①はA水準のみ努力義務となる.
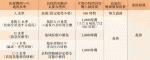
III.臨床研修病院における働き方改革―当院での取り組み―
医師の働き方改革はあくまでA水準が原則であり,追加的健康確保措置を遵守するために各診療科所属長や人事課担当者等に課せられる労務管理の相当な労力も考慮すれば,大学病院を除いた一般市中病院ではA水準を目指した医師労働時間短縮計画を策定することが現実路線と考える.当院も「臨床研修医を含めた全診療科原則A水準」を目標に,各方面から検討し対策を講じた.
① 勤怠管理システム
「働き方改革関連法」では,客観的労働時間の記録が義務化された.当院ではICカード打刻による独自開発の勤怠管理システム「Perfect Webee」を2005年より導入していたが,より効率的な勤怠管理を目的に2023年9月より新勤怠システム“TimePro-VG”(AMANO corporation,横浜)を新規導入した.これにより,複数の非連続勤務の登録(一度退勤した後の緊急呼び出しなどによる再出勤)・兼業などの院外業務登録による正確な労働時間把握,時間外勤務時間・自己研鑽時間・在院時間等のリアルタイム算定,などが可能となった.
②宿日直許可
宿日直中の勤務実態が,労働密度が低く十分な休息を取ることが可能と認められる場合は,労働基準監督署から宿日直許可を得ることができ,その時間帯は時間外労働時間規制の対象から除外される.宿日直許可は一部の診療科・ユニット・職種(臨床研修医や専攻医など)や限られた時間帯でも申請可能である.当院は1974年に宿日直許可を取得しているが,現在の宿日直体制の勤務実態と相容れない診療科や時間帯があるので,宿日直帯時間帯の実労働実績を調査した.
③勤務実態の把握
2022年度在籍の全常勤医師327名(医員以上197名,内科系専攻医68名,外科系専攻医28名,臨床研修医34名)の2022年4月~2023年3月の勤務実態を調査したところ,宿日直帯の実労働時間を含まない場合は,時間外労働時間が年960時間を超えた医師は1名のみ(心臓外科副部長)であった.次に,2023年4月5月2カ月間の宿日直当直帯実働時間をアンケート調査したところ,労働密度に応じて職種が次の3パターンに分類可能であった.
パターンA(労働密度大):臨床研修医/内科専攻医/外科専攻医/小児科
パターンB(労働密度中):内科医員以上/産婦人科/麻酔科/ICU/CCU/SCU
パターンC(労働密度小):外科医員以上
この実測データを基に,各職種パターンの平日宿直・休日日直・休日宿直の想定実働時間を2022年度の実測時間外労働時間に加算すると,年960時間超えの医師は17名と判明したが,最大1,200時間までであり,単純計算で月10時間の時間外労働縮減で全医師がA水準に到達可能なレベルであった.なおこの17名は1名を除くと全て専攻医であった(内科系13名,外科系3名(整外/脳外/眼科)).
④宿日直体制の見直し:
全職種で深夜帯の労働密度は低いことが判明したので,現在の宿日直許可を維持しつつ,労働密度が高い準夜帯の勤務シフト・宿直時間を改定した.外科専攻医の平日宿直の勤務シフト変更例を示す(図1a).宿直日(水曜)は,現行では日勤から宿直の連続勤務であるが,シフト制導入後は14:20までは勤務なし(休息)となり,14:20~23:00は遅出勤務として扱い,17:25までは各診療科の業務に,17:25以降は病院の宿直業務を通常時間内業務としてこなす.そして,23:00~翌8:45は本来の宿直業務に従事する.
一方,宿直日の午前から外来業務や予定手術があり遅出出勤ができない場合は,フレックス制(図1b)を導入することで対応する.例えば労働密度の低い月曜からA時間,金曜からB時間の計A+B時間を,宿直日水曜の遅出出勤時間までの労働時間に振り替える.このA+B時間は時間外労働にはならず,月曜のA時間と金曜のB時間は勤務なし(休息)となる.このフレックス制を適用すれば,非手術日の勤務時間を割り振ることで,専門研修に必要な手術への参画が可能となり,手術手技向上の機会が減るリスクは回避できる.
⑤タスクシェア・シフト
外科専攻医は外来・手術・術後管理・病棟業務・各種事務処理等の日常臨床業務に加えて,臨床研修医や医学部臨床実習生の直接指導も担当する立場であり,必然的に時間外労働時間が長くなる.当科では労務負担を軽減するため,専攻医に外来業務は課していない.またチーム制の導入も有用な対策の一つだが3),当科はスタッフの数もそれ程多くないため,臨機応変柔軟に科全体でお互いをカバーし合う体制を選択している.なお入院患者は複数主治医制(臓器別指導医-医員または専攻医-臨床研修医)としており,上級医と下級医の間で適宜業務をタスクシェアしている.また,夜間・休日の当番制(主として緊急手術の呼び出し)も以前から導入しており,オンオフのメリハリを持って業務に臨めるようにしている.
医師の労働時間短縮推進には,医師以外の他職種に業務をタスクシェア・シフトするのも有効である.当院でも専門委員会で議論を重ね,看護師・薬剤師・事務職等とのタスクシェア・シフト方策を実践化してきたが,留意するべき点は,シェア・シフトされた側の業務量は逆に増えてしまい,組織全体では根本的な解決策にならない事である.すなわち,不要な業務を削減する“タスクリダクション”の意識をもって臨むことが実は重要で,われわれも不要で無意味な書類作成や確認・承認行為を洗い出して,業務そのものを縮減するように取り組んでいる.
タスクシェア・シフトに直結する最も有用な方策は,医療事務作業補助者Medical Clerk(MC)の採用である.当院では,診療録等の代行入力・各種書類記載・問診票による患者病歴聴取・検査説明など診療に直結する医療事務を委託できるSpecial Medical Clerk (SMC)制度を2012年より導入した.外部からの募集のみでなく,院内でのSMC育成システムも整備化され,現在では各診療科に1名配置できるほど増員されている(2023年8月現在33名).特に外科医の立場では,相当な時間と労力を要するNational Clinical Database (NCD)へのデータ入力を委託できる点で,SMCの貢献度は極めて高いと考えている.
また,厚生労働省が認定している21区域38行為の特定行為を全てあるいは部分的に実践できる「特定看護師」2)や,包括的指示による特定行為実践だけでなく,医師からの直接指示による相対的医行為が実践できる「診療看護師(Nurse Practitioner)」の存在意義も極めて重要で,外科術後病棟管理やICU・HCU領域の特定医療行為の代行は有意義なタスクシェア・シフトになる.ただしこれらは相当数の特定看護師・診療看護師が配置されないと,医師の勤務時間短縮に対する貢献は可視化されにくいのが現状で,中長期的視点で取り組むべき課題と考えている.
⑥時間外勤務管理の徹底
1)毎日の出退勤の打刻義務化:打刻が無ければ欠勤扱い,管理職も打刻必須.
2)時間外勤務(上司の指示・命令が必須)と自己研鑽の定義を周知徹底.
3)早出・遅出勤務の導入:診療科全体や医師個人が勤務開始・終了時間をずらす早出・遅出勤務を承認.
4)ノー残業デイの設定:各科で週1回選定.
5)時間外勤務申請の締めを月2回に設定(当月15日,翌日3営業日):A水準でも面接指導が義務化され,疲労蓄積が想定される80時間前後のタイミングが望ましいとされているが,当院では先行対策として,半月で40時間超の医師に対して面接指導を早期導入する事とした.診療科所属長は半月毎にスタッフの勤務状況を把握し,科内医師間でのタスクシフト・シェアを早急に検討する.
6)時間外労働勤務状況実績の共有:部長以上の管理職に全医師(個人名は臥せる)の実績一覧を毎月報告する.

IV.おわりに
より安全でより確実な医療を提供するために,まずわれわれ外科医自身,特に管理職の立場にある外科医はより一層率先して自らの労働環境を見つめ直すことが重要である.外科医に課せられた業務ミッションは膨大ではあるが,各医療機関が工夫を凝らしていろいろな策を練り,外科医の負担が少しでも軽減し,仕事に対するやりがいが向上する環境を作り上げることが必要である.
利益相反:なし
文献
1) 厚生労働省 医師の働き方改革ホームページ.2023年8月15日. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html
2) 厚生労働省 特定行為に係る看護師の研修制度ホームページ.2023年9月8日. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
3) 黒田 慎太郎 , 大段 秀樹 :働き方改革における当直業務の適正化とチーム制・オンコール及び当番制導入について.日消外会誌,56:126-131,2023.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。