日外会誌. 125(1): 56-62, 2024
特集
学会活動,診療・研究にSNS等のツールをどう活用するか
8.研究者のためのSNS活用法
|
大阪医科薬科大学医学研究支援センタートランスレーショナルリサーチ部門/一般・消化器外科学教室 谷口 高平 |
研究者がソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を利用して情報を発信する際,情報の受け手の特性を考慮して適切なSNSを選択することが重要である.研究者でコミュニティが形成されているSNSをアカデミックソーシャルネットワーク(ASN)と呼び,国際的なASNにResearchGateなどがある.本邦で最大のASNは国立研究開発法人科学技術振興機構が運営するresearchmapであり,研究者同士の交流から業績の半自動登録まで,多岐にわたる機能を提供している. 科学研究費助成事業の電子申請システムとの連携などを経て,利用者数は増加の一途を辿っている.また,研究者の一意識別のための国際的な識別子であるORCID iDを紐付けておくことが重要である.さらに,近年,クラウドファンディングを活用した研究資金の調達が増えており,一般的なSNSを使って研究内容を広く伝えることが不可欠である.特にASNは,研究者の業務負担を軽減し,研究活動を促進する目的で提供されており,多くの研究者や機関が共通のプラットフォームとして利用することで,その効果はさらに増大すると考えられる.
キーワード
SNS, アカデミックソーシャルネットワーク, researchmap, ORCID, クラウドファンディング
I.はじめに
この原稿の執筆を依頼された際,筆者の周囲の研究者に研究活動にソーシャルネットワーキングサービス(SNS)をどの程度活用しているかを尋ねたが,肯定的な反応は得られなかった.筆者自身も,日常的に研究にSNSを頻繁に取り入れているわけでは決してない.しかし,多くの研究が公的資金を用いて行われており,その活動や成果を情報公開することは,研究者の責務という認識も定着している1).さらに,近年では人工知能(AI)技術を活用したツールやアプリが増加し,われわれの生活により身近な存在となっており,研究活動にも取り入れることが求められる.本稿では,研究者がSNSを利用する意義や目的を再評価し,アカデミックソーシャルネットワーク(ASN)や関連するトピックについての現状を整理し,筆者の見解を共有する.
II.研究者がSNSを活用する目的とは
SNSとは,FaceBook,X(旧: Twitter),Instagramなどに代表される登録された利用者同士が交流できるWebサービスで,今や情報の発信だけでなく,情報収集の主要な手段としても利用されている.では,研究者が情報を活用(特に発信)する目的は何だろうか?このことを考える際には,情報の受け手を想定すると比較的整理しやすい.
情報の主な受け手として同業者を想定する場合は,自身の研究成果を他の研究者と共有し,研究内容に関する意見交換や,新たな共同研究の機会を模索することである.一方,非同業者を想定する場合は,一般の人々に対して公的研究費の使用に関する成果の説明(社会的責務)と,研究の出口戦略である産業界との連携がその目的となるだろう(表1).昨今のわが国の経済状況を考慮すると,国民の理解を得るための情報公開や,研究成果の社会実装という面が特に重要視される.研究者は,学術研究の「真理の探究」といった側面だけでなく,研究の成果を如何に社会に還元するかということに意識を向けざるを得ない.このように考えると,研究者がSNSで情報発信を行う際には,その他の情報発信の場合と同様に,受け手,すなわちその情報を誰に向けて発信しているのか?を明確にする必要がある.理想的には,情報の受け手の区分をボーダレスに満たす情報発信ツールが存在するのが望ましい.

III.アカデミックソーシャルネットワーク
ASNとは,SNSの中でも特に研究者間でのコミュニティが形成されるものを指すと理解している.研究者には個別のプロフィールページが設けられ,研究者同士の交流(研究へのコメント,出版物の共有,メッセージ交換など)が可能である2)
3).この意味では,前述の一般的なSNSも広義のASNに含まれる.ASNの主要な五つの機能として,①オンラインペルソナの管理(インターネット上での自己イメージやアイデンティティをどう構築するか),②研究成果の拡散,③研究者間の協力の促進,④研究情報の整理と管理,⑤研究の影響度の測定が提示されている4).
代表的な国際的ASNとしては,ResearchGate(https://www.researchgate.net/)や,Academia.edu(https://www.academia.edu/)が挙げられる.個人的体感としては,ResearchGateの方が普及している印象で,筆者も登録している.今回の寄稿のために,恥ずかしながら,久しぶりにResearchGateの自分のページを訪れた.前回の訪問からかなりの時間が経過していたにも関わらず,論文業績は最新のものまで更新されていた.この機能(AIによる論文業績の自動追加)が実装されているのは,手入力の手間が省けるため非常に便利である.
ResearchGateには自身の論文をアップロードする機能や,論文の提供を著者に依頼する「request」機能が搭載されている.自施設から目的の論文にアクセスできない場合に,その著者がResearchGateに該当の論文を公開していれば,ダウンロードが可能である.公開されていない場合でも,著者が要望に応じてくれれば論文を入手することができる.これは確かに便利な機能である.実際,本邦で研究に従事する研究者508名を対象としたResearchGate利用に関するアンケート調査によれば,ResearchGateの利点として「論文へのアクセスを得る」が最も多い回答(113名)であった3).一方で,「研究を普及させ,研究者のプロフィールを構築する」は50名で第三位,「他の研究者とのコミュニケーション」は35名(第四位)に留まっている3).この結果から見ると,一般的なSNSが本来有するコミュニティ機能というよりは,文献アクセスのためのツールとしての側面が強いのかもしれない.
しかし,requestの要望に応じる際には,慎重な判断が必要である.特に,論文をアップロードする時には,著作権に関する十分な配慮が不可欠で,出版社との契約内容を遵守する行動が求められる.少なくとも,オープンアクセスでない論文を無許可で公開することは避けるべきであろう.この点において,2017年に大手出版社であるACS,Elsevier,Wileyなどが連合し,ResearchGateに対して著作権侵害の申立てを行った.これを受けて,ResearchGateは約170万本の論文へのアクセスを制限するという処置を講じている5).したがって,ResearchGateの利用に際しては適切なリテラシーが求められる.
一方,h-index(論文がどれだけ他の研究者に引用されているかを示す指標)を瞬時に確認できるのは便利である.また,Statsという機能を利用すると,自身の論文がどれだけ閲覧されているかを把握することができる.興味のある方は,活用を検討されてはいかがだろうか.
IV.researchmapの活用
researchmapは,国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が提供する研究者総覧データベースである.現在,約32万人もの研究者が登録している国内で最大のASNである.Web上での研究活動(研究成果の管理・公開や,研究者同士のコミュニケーション)を目的として国立情報学研究所で運用していたResearchmapと,産業界での研究成果の活用を目的としたJSTのReaD(研究開発支援総合ディレクトリ)が2011年に統合されて,誕生したものである1)
6).researchmapの登録者数は年々増加しており,年間ページ閲覧数は1億8,000万pvを超えるなど,研究者の利用が広がっていることが伺える(図1).
科学研究費助成事業(科研費)の電子申請システムとの連携がresearchmapの利用拡大の大きな要因となったと考えられる.2018年度より,研究計画調書の「研究業績」の項目が,「応募者の研究遂行能力及び研究環境」に変更され,研究業績に関しては,審査委員が必要に応じてresearchmapの情報を参照できるようになった.この変更を受けて,筆者もresearchmapのページを更新したのを覚えている.researchmapは,公募型の研究資金制度を管理する府省共通研究開発管理システム(e-Rad)と連携しており,科研費だけでなく,他の競争的資金制度においても登録情報の活用が促されている6).この取り組みの背景には,研究者の研究活動に伴う事務作業(申請・報告・調査書の作成など)が肥大化し,研究時間が枯渇していることが挙げられる.つまり,researchmapは,研究者の事務的な負担を軽減し,研究活動をより円滑に進めるための支援システムとして提供されているのである1)
6).
前述の,「情報を受け取る側の区分をボーダレスに満たすツール」としても,researchmapは多岐にわたる機能を有している.例えば,コミュニティ機能を使えば,研究者間での情報の共有や共同プロジェクトの管理が行える.実際の活用例として,「次世代脳」プロジェクトには2,000人を超える参加者がいる7).さらに,研究の進捗や意見を公開するブログ機能や8),自らの研究資料をアップロードして共有する機能も備えている.夏休みの自由研究のアドバイスなどを資料公開している研究者もおり9),その活用方法には実に多様性がある.
その他にも,大学の研究者総覧をはじめとする機関システムとの連携や,従来の業績情報の自動登録機能に追加して,競争的資金と業績を紐づける機能,本人以外による業績管理機能(代理人機能),プレスリリース機能などの多彩な機能が搭載されている(表2).
researchmapを最大限に活用し,競争的研究資金の申請や成果報告,機関による研究者の評価などをこのシステムを用いて一元的に実施することで,研究者の研究以外の作業負担が軽減されることを強く希望する.この機会に,ご自身のresearchmapの見直しを行うと共に,各機関で定期的なメンテナンスが継続的に行える体制を構築することをお勧めしたい.
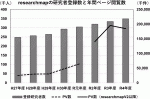
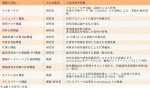
V.ORCID (Open Researcher and Contributor ID)の活用
ORCID(オーキッド)とは,2010年に米国で設立された,国際的に研究者識別子に取り組む非営利法人ORCID Inc.が付与する,世界中の研究者を識別するための個人ID(ORCID iD)である10).すなわち,人間版のDigital Object Identifier:DOIだと筆者は認識している.ORCID iD は,研究者とその研究成果である論文や著書などを正確に結びつける,いわゆる「名寄せ」の機能を提供している.研究活動は,芸術,芸能,政治活動と並び,個人の名前が重要となる分野である10).しかし,Webの普及とともに,研究関連情報の増加や研究のボーダレス化が急速に加速し,伝統的な方法である著者名を用いた研究者情報や関連論文の検索が難しくなってきた.具体的には,①同姓同名,②結婚などによる改姓,③所属機関の変更や異動,④研究IDを提供するサービスの過多,⑤組織による所属研究者の情報を集約する難しさなどの問題が存在する10).筆者も,改姓の経験があり,現在の氏名では,検索できない論文が幾つか存在する.ORCIDの取り組みは,全ての研究者に固有の識別子を提供することで,このような課題を克服し,学術コミュニケーションを円滑にすることを目指している.
研究活動には,研究者個人,研究機関,学会,出版社,資金提供機関など多くの人や組織が関与している.そのため,ORCID iDの様に国際的に統合された研究者IDは,多様な関係者に恩恵がある.身近な例では,論文を投稿する際に,以前は,ジャーナルごとに新しいIDを作成する必要があったが,最近では,ORCID iDの入力で代用できることがほとんどになった.これは,各出版社や,PubMed(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)の様な多くのユーザーを持つの既存のシステムとORCIDが連携しているからである.
ORCID iDの取得方法は決して難しくなく,ORCID Inc.のウェブサイト(https://orcid.org/)の「SIGN IN/REGISTER」から,基本的な情報(名前・メールアドレス・パスワード・公開/非公開など)を入力するだけで,IDである16桁の数字が付与される.また,JSTは,ORCIDのメンバーシップを取得しており,先に触れたresearchmapにもORCID iDを登録可能である6).国内の研究者識別子である研究者番号と,国際的な研究者識別子の紐付けをresearchmapを通じて行うことは,研究者の正確な識別に非常に役立つと考える.ぜひ,ORCID iDの取得とresearchmapへの登録をお勧めしたい.
VI.クラウドファンディングによる研究資金調達
研究活動には,資金の確保が欠かせない要素である.科研費や,国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の事業補助金といった競争的研究資金では,全ての応募者が資金を得るわけではない.実際,令和4年度の科研費の新規採択率は28.6%となっており11),狭き門と言える.また,研究のトピックや方向性には少なからずトレンド(趨勢)が存在し,時代や背景によって研究資金の取得のしやすさも変化する.研究資金が一旦途切れると,新しいアイディアや挑戦的な実験を進めることが難しくなり,さらなる資金の獲得も困難になるという負のスパイラルに陥りやすい.この状況を回避するためには,継続的な資金獲得が不可欠であるが,前述の通り,それは決して容易ではない.このような背景から,近年では,クラウドファンディングを利用した新たな研究資金調達方法が注目され,徐々に導入されてきている12)
13).
クラウドファンディングとは,「群衆」(crowd)と「資金調達」(funding)の造語である.この方法では,プロジェクトの主催者が特定のプラットフォーム(資金調達をサポートするオンラインサービスやウェブサイト)に協力を依頼し,インターネット上で不特定多数の人々に資金提供を呼びかける.そして,プロジェクトの目的や内容に共感した人々(支援者)から資金を募る仕組みとなっている12)
14).
本邦における学術分野のクラウドファンディングのプラットフォームとしては,academist(https://academist-cf.com/),READYFOR College(https://readyfor.jp/lp/college/),Otsucle(https://otsucle.jp/)などが挙げられる.クラウドファンディングは,寄付型(税額控除が受けられる),購入型(プロジェクト関連の商品やサービスを購入する),金融型(株式・融資・ファンドとしての投資)の三つに分類される.医療や学術系のクラウドファンディングは,主に寄付型に該当する.また,実施方式としては,目標金額を達成した場合のみ資金が受け取れるAll or Nothing型と,目標金額の達成に関わらず資金を受け取れるAll In型の二つが存在する14).
個人的に,近隣の関西医科大学で,膵がん腹膜転移に対するS-1+パクリタキセルの経静脈・腹腔内投与に関する無作為化比較第Ⅲ相試験のクラウドファンディングが実施され,一次目標金額の1,000万円がプロジェクト開始からわずか2日で達成されたことは記憶に新しい14)
15).また以前の同僚である研究者も,フキノトウに含まれるペタシンの創薬研究のためのクラウドファンディングを実施し,目標金額を大きく上回りプロジェクトを成立させている16).その他にも検索すると,多くの医療や学術関連のクラウドファンディングの存在が確認できる.これは,多くの人々が健康や医療に関心を持ち,医学の進歩に貢献したいと考えていることを示唆している.
支援者を募る際に重要な点は,多くの対象者が医療の専門家でない一般の人々(非医療従事者)であるため,研究の意義や必要性をわかりやすく,魅力的に伝えることである.そのため,競争的資金を獲得するための申請書とは異なり,平易な言葉で,視覚や聴覚にも訴えかけるアプローチが必要となる12).つまり,YouTube,X,Instagram,FacebookなどのSNSを効果的に活用することが不可欠である.
VII.おわりに
多くのSNSやASNが時代とともに登場し,淘汰の中で真に価値あるものだけが生き残っていく.その価値とは,利用者がそのプラットフォームを活用した際に,なんらかの「得」を感じることではないだろうか.それは,記事の既読数や「いいね!」の様な簡単なフィードバックから,論文の取得,研究資金の確保,新しい共同研究の機会の創出,事務的な手間の削減,など多岐にわたる.多くの研究者は多忙で,新しいシステムを導入するための時間が限られている.しかし,そのシステムが提供する対価が時間や労力の投資に見合っていれば,そのシステムは広く受け入れられることが期待される.
また,このようなプラットフォームは,多くのユーザーが参加することでその価値が増大すると言える.筆者自身も,ASNの更なる活用の余地を感じており,この機会にASNとの関係を強化したいと思っている.本稿を参考に,皆様がご自身の環境を見直し,研究の一助として活用していただければ幸いである.
謝 辞
researchmapに関する資料をご提供いただいた国立研究開発法人科学技術振興機構情報基盤事業部サービス支援センターのresearchmap関係者様,原稿の校閲をしていただいた大阪医科薬科大学医学研究支援センタートランスレーショナルリサーチ部門の小野富三人先生と,一般・消化器外科学教室の李相雄先生,そして今回の寄稿の機会を提供してくださった平松昌子先生に心から感謝申し上げます.
利益相反:なし
文献
1) 新井 紀子 :研究資源・研究情報のエコサイクルの確立を目指してReaDとResearchmapの統合がもたらすもの.情報管理,54(9): 533-544, 2011.
2) Manca, S., & Ranieri, M. (2017). Editorial:Reshaping professional learning in the social media landscape—Theories, practices and challenges. Qwerty, Open and Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education, 12(2), 5-11.
3) Shannon M , Yusuke S :A ResearchGate-way to an international academic community? Scientometrics, 126(2): 1149-1171, 2020.
4) Hagit M-T , Efrat P :Why Do Academics Use Academic Social Networking Sites? The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 18(1): 1, 2017.
5) 国立研究開発法人科学技術振興機構:ニュース(STI Updates). 2017年11月16日 出版社連合,著作権バトルでResearch Gateにより一層強固な姿勢. 2023年9月12日. https://jipsti.jst.go.jp/sti_updates/2017/11/10161.html
6) 粕谷 直 . 研究者総覧データベースresearchmapのこれまでとこれから. 情報の科と技, 71(5): 214-219, 2021.
7) researchmap:「次世代脳プロジェクト」.2023年9月12日. https://researchmap.jp/community-inf/Comprehensive-Brain-Science-Network
8) researchmap:池田嘉郎. 2023年9月12日. https://researchmap.jp/read0209500/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0?frame_id=561056
9) researchmap:荒木健太郎. 2023年9月12日. https://researchmap.jp/kentaro.araki/%E8%B3%7%E6%96%99%E5%85%AC%E9%96%8B
10) 蔵川 圭 , 武田 英明 :研究者識別子ORCIDの取り組み.情報管理,54(10): 622-631, 2012.
11) 日本学術振興会:科研費の主な研究種目における応募件数,採択件数,採択率の推移. 2023年9月12日. https://www.jsps.go.jp/file/storage/grants/j-grantsinaid/27_kdata/data/r04/2-1_r4.pdf
12) 土肥 洋一郎 , 筧 善行 , 杉元 幹史 :研究資金獲得のためのクラウドファンディング活用. 日排尿機能会誌,32(2): 479-482, 2022.
13) Schucht P , Roccaro-Waldmeyer DM , Murek M , et al.:Exploring Novel Funding Strategies for Innovative Medical Research: The HORAO Crowdfunding Campaign. J Med Internet Res, 22 (11):e19715, 2020.
14) 里井 壯平 , 山本 智久 , 山木 壮 , 他:FOCUS クラウド ファンディングで研究資金を集める!-臨床研究(先進医療制度を利用した特定研究)から得た経験.臨外,77(6): 748-753, 2022.
15) 膵がん腹膜転移の患者さんに希望の光を.新しい治療法の挑戦へ. 2023年9月12日. https://readyfor.jp/projects/suigan
16) 岐阜大学:フキノトウから副作用の少ない抗がん・転移阻害剤の開発へ. 2023年9月12日. https://readyfor.jp/projects/fukinoto#%EF%BC%91
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。