日外会誌. 121(5): 503-509, 2020
特集
改めて認識する小児急性腹症治療に対する外科医の役割
4.急性虫垂炎
|
東京都立小児総合医療センター 外科 下島 直樹 , 月崎 絢乃 , 東 紗弥 , 原田 篤 , 石塚 悦昭 , 水野 裕貴 , 石濱 秀雄 , 加藤 源俊 , 富田 紘史 , 下高原 昭廣 , 広部 誠一 |
小児の急性虫垂炎は急性腹症における最も頻度の高い疾患である.にもかかわらず正確な診断が難しいことが少なくない.
最新のNational Clinical Database報告によると,小児の急性虫垂炎治療は小児外科認定施設,教育関連施設以外の病院で約7割が施行されており,一般消化器外科医を中心とした,小児外科を専門としない医師によって多くの症例が治療されている実情がある.
まず確定診断をつけ,次に治療方針を立てていく過程で問診,理学的所見に加えて超音波による重症度評価を正確に行うことが重要である.われわれの施設では虫垂の層構造と血流の評価をすることで,重症度を分類し,それに基づいた治療方針を立てている.抗菌薬不要の軽症例から緊急手術を検討すべき症例,抗菌薬治療を先行させて待機的虫垂切除をプランする症例などに分類することで,それぞれの症例に適した治療が可能となる.
診療にあたる外科医全員が小児急性虫垂炎の臨床像をよく理解し,適切な診断,治療を提供するのが“外科医”としての重要な役割である.
キーワード
急性虫垂炎, 小児, 待機的虫垂切除術, 腹腔鏡下虫垂切除術
I.はじめに
急性虫垂炎は小児の急性腹症をきたす日常的な疾患であるが,その症状や臨床像は多様であり,正確な診断が難しいこともしばしば経験する.以前は小児の急性虫垂炎は進行が早く,穿孔防止のためには診断がついたら早期手術を行うべきであるという考え方が一般的であったが,最近は軽症例に対する保存的治療が奏効することや,重症例の場合は抗菌薬治療で炎症を抑えてから待機的虫垂切除を行うことの有用性が広く受け入れられ,必ずしも診断から直ぐに外科治療に踏み切るばかりでは無くなっている.今,外科医はより正確な虫垂炎の診断と重症度評価,それに応じた治療方針計画と安全で合併症の少ない手術の全てを求められている.
II.小児急性虫垂炎の現状
小児,成人を問わず,急性腹症における外科疾患で急性虫垂炎は最も頻度が高い.National Clinical DatabaseのAnnual Report 2015-20161)によると,common diseaseであること,10歳以降の年長児症例も多いことからか,意外にも小児の急性虫垂炎は小児外科認定施設や教育関連施設よりもその他の一般病院で多く手術を施行されている(表1,図1).また,施設ごとで選択されている術式を比較すると,認定施設では88%が腹腔鏡下手術であるのに比べその他の一般病院では66%にとどまる.まさに急性虫垂炎の外科治療が様々な規模の医療機関,専門背景の異なる外科医によって治療されている現状を良く表しており,小児外科医,成人外科医それぞれが小児急性虫垂炎の臨床像をよく理解し,適切な診断,治療を提供するのが“外科医”としての重要な役割となっている.
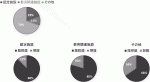

III.小児急性虫垂炎の診断
小児急性虫垂炎の多くが腹痛,嘔気,嘔吐,発熱などの症状で発症し,次第に限局する右下腹部の痛みとして疑われることが多い.その診断プロセスとしては開業医や一般市中病院の小児科を経由して,総合病院,小児病院,大学病院など外科治療の可能な施設に紹介されることが多い.
われわれの施設は東京の多摩地区にある小児医療センターであるが,年間200件近くある急性腹症で外科コンサルトとなる症例の半数近くを急性虫垂炎が占める(図2).診断においては,問診,理学的所見をとったのち,腹部超音波検査による確定診断と重症度の評価を行う2)3).6ミリ以上に腫大した虫垂の存在と,同部に圧痛を認めることから虫垂炎の確定診断とする.虫垂周囲に高エコーの脂肪織が取り囲んで一塊となっている場合,腫瘤形成性虫垂炎と診断される.一方,低エコーで不整な形状の液体貯留を虫垂周囲や骨盤底などに認めた場合,既に虫垂が穿孔し膿瘍を形成している所見と考える.
虫垂壁の層構造と壁内の血流変化は虫垂炎の病理組織所見との相関があるとされており,重症度を決める上で重要である.われわれの施設では層構造が明瞭で乱れを認めないものをgrade Ⅰ,不整となっているものをgrade Ⅱ,消失しているものをgrade Ⅲと分類している(図3).それぞれ,病理組織所見におけるカタル性,蜂窩織炎性,壊疽性に相当する4).また,grade Ⅱを壁内の血流亢進所見を認めるgrade Ⅱaと血流低下所見を認めるgrade Ⅱbに分け,両者が治療方針を決定する上での重要な境界と位置づけている.すなわち,grade Ⅱaの急性虫垂炎は自然治癒傾向があり,抗菌薬投与は不要で補液のみで症状改善すれば入院治療は不要である一方,grade Ⅱbは炎症が進行して膿瘍の発生を認めることがあるため,入院の上,抗菌薬治療の方針としている.
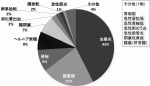
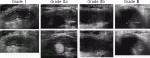
IV.小児急性虫垂炎の治療
急性虫垂炎の治療の本幹は虫垂切除術による外科的治療であるが,炎症の重症度によっては自然に治癒する症例もある.われわれの施設では超音波による重症度分類によって治療方針を決定している(図4).超音波による重症度分類でgrade Ⅰ,Ⅱaと診断された群は抗菌薬を使用せずに保存的治療で経過観察し95%が初期治療に成功している5).しかし,遠隔期再発を25%に認めており再発例に対しては外科治療を行っている.grade Ⅱb,Ⅲと診断された群は入院の上,抗菌薬治療を行っている.膿瘍形成の無い場合はアンピシリン/スルバクタム150mg/kg/dayで治療し,膿瘍形成を伴っている場合はセフォタキシム150mg/kg/dayを加えた2剤による治療を行っている.毎日の問診,理学的所見に加えて,3日ごとに血液検査と超音波検査を行い,抗菌薬治療終了基準(表2)を満たした場合に退院とする.退院後は待機的虫垂切除術を計画するが,待機期間は3カ月以上とし,膿瘍形成性の場合は膿瘍消失が確認されてからの待機期間で手術時期を決定している.2017~2019年の3年間で術前に急性虫垂炎と診断され虫垂切除術を施行した症例は179例で,急性期に癒着性腸閉塞を合併して緊急手術を施行した3例を除き176例(98%)が腹腔鏡下手術であり,開腹コンバート症例は認めなかった.158例(88%)が待機的虫垂切除術でありほぼ全例が術後3日目に退院していた.待機的虫垂切除術症例には3例,急性期の膿瘍形成に対して,膿瘍穿刺ドレナージが施行されていた.いずれも全身麻酔下に経直腸ダグラス窩膿瘍穿刺ドレナージをエコーガイド下に施行されており,1例は経腹的穿刺ドレナージも同時に施行されていた.これら3例の待機的虫垂切除術時の癒着はいずれも軽度であり,急性期の穿刺ドレナージは症例を選択して施行することで入院期間の短縮とより安全な待機的虫垂切除術につながる可能性が示唆された.
これまでの経験上,入院時にⅡb,Ⅲ症例で膿瘍形成を認めていなかった症例が入院経過中に穿孔して膿瘍形成する症例を一部に認めることから,2018年6月より穿孔のリスクを高める四つの因子(反跳痛,腹水貯留,白血球数18,000/µl以上,発症から24時間以上経過)を用いてリスク評価し,スコアが4点以上の場合には穿孔のリスク50%と予測して積極的に緊急で虫垂切除術を検討するように方針を変更した6)(表3).2019年12月までに穿孔スコア4点以上の11例に対して緊急手術を施行しているが,全例,腹腔鏡手術にて虫垂切除ができており,手術時間は中央値75分(41~169分)で術後合併症は認めていない.退院まで要した治療期間は平均術後5.2日(3~8日)であり,Grade Ⅱb,Ⅲで入院加療された群の平均入院期間が約2週間であることを考えると安全に治療期間の短縮を実現できている実感がある.今後,入院後の穿孔症例をどの程度減らすことができたかを検証していく必要がある.
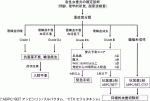
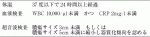
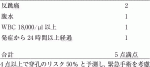
V.急性期の腸閉塞合併症例
2017~2019年の3年間で急性期に腸閉塞を合併し緊急手術となった症例が4例(2%)あった.そのうち1例は腸閉塞で緊急入院となり腹部造影CT検査で絞扼性腸閉塞と診断され緊急開腹手術を行ったところ小腸の著明な拡張と多量の排膿を認め,急性虫垂炎による炎症で小腸が癒着を起こしていた.他の症例も全例膿瘍形成性虫垂炎で,術前にCTによる画像診断がなされていた.膿瘍の近傍に口径差を認める小腸の描出が特徴的であった(図5).炎症の強い虫垂炎の場合麻痺性イレウスを併発することもあるが,癒着による器質的な通過障害を臨床経過と画像所見から鑑別し,適切なタイミングで手術適応の判断をすることも外科医に求められるスキルと言える.
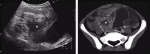
VI.おわりに
小児急性虫垂炎の診断と治療の現状および当院における診療内容について述べた.抗菌薬治療をせずに自然に症状が改善するものから早期に膿瘍形成して腸閉塞を来す症例まで様々であるが,超音波検査による重症度分類を正確に行い,治療アルゴリズムに沿った診療を行う事で個々の症例に適した治療選択が可能となる.様々な専門背景をもつ外科医の皆さんにとって日常診療の一助になれば幸いである.
利益相反:なし
文献
1) 臼井 規朗,岡本 晋弥,上原 秀一郎,他:National Clinical Database(小児外科領域)Annual Report 2015-2016.日小外会誌,55:298-303,2019.
2) 加藤 源俊,下島 直樹,富田 紘史,他:【動画で見せます,小児外科疾患】小児急性虫垂炎における画像診断の有用性.日小児放線会誌,35:72-77,2019.
3) 富田 紘史,加藤 源俊,下島 直樹,他:【ここが危ない小児診療のピットフォール:日常診療編】急性虫垂炎の診断.小児外科,50:796-798,2018.
4) 志関 孝夫,鎌形 正一郎,広部 誠一,他:超音波所見による小児急性虫垂炎の手術適応 特にパワードップラー法の有用性について.日小外会誌,42:16-22,2006.
5) 鎌形 正一郎:外科関連消化器疾患(肥厚性幽門狭窄症,胃食道逆流症,急性虫垂炎)の治療 小児外科医と小児内科医のstrategy 小児急性虫垂炎に対する診断と治療戦略.日小児栄消肝会誌,23:96-101,2010.
6) 加藤 源俊,藤村 匠,下島 直樹,他:急性虫垂炎に対する保存的治療の功罪 穿孔に至るリスク因子の検討.日小外会誌,54:708,2018.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。