日外会誌. 123(4): 330-338, 2022
特集
医療訴訟のここがポイント―外科医にとって今必要な知識―
6.診療拒否に関する訴訟―特に患者側の迷惑行為について―
|
弁護士法人棚瀬法律事務所 棚瀬 慎治 |
医療者の診療拒否の是非が争われた裁判例64件の分析を行ったところ,応招義務違反など医療者の行為の違法性が認められた裁判例は11件にとどまった.
患者側の迷惑行為や,医療者と患者側との間の信頼関係の喪失を原因として診療拒否がなされた類型については,ほとんどの裁判例において医療機関側の主張が認められており,そもそも患者の主張するような診療拒否自体が存在しないと認定する裁判例もみられた.
患者の迷惑行為などで診察治療を実施することが困難な事案においては,診療の提供を行わないという選択肢もあり得ることが示唆された.
キーワード
応招義務, 診療拒否, 訴訟, 裁判例
I.はじめに
医師法19条1項は,「診療に従事する医師は,診察治療の求があった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない.」として,いわゆる医師の応招義務(または「応召義務」)を定めている.
医師の応招義務の沿革は古く,明治7年の醫制44条にて医師が「業ヲ怠リ危急ノ用ニ達セサル時」には医業停止の対象となるとされたのにはじまり,その後は根拠規定が変遷し,旧刑法(明治13年)427条,警察犯處罰例(明治41年)3条7号,旧医師法施行規則(大正8年)9条の2,国民医療法(昭和17年)9条を経て現行医師法(昭和23年)19条1項にて規定されるに至っている.歯科医師,薬剤師,助産師および獣医師についても,それぞれの規制法にて応招義務が規定されている.
その趣旨については,経済的弱者の保護,ひいては社会の善良なる秩序に対する危害防止にあるとする見解1)や,医師が医業を独占する一種の公的性質を有する機関であることを根拠とするとの見解2)などが伝統的に唱えられてきており,裁判例においては,患者に医療へのアクセスを保障して,患者の生命・身体の侵害の保護を図ることにあるとするもの(後掲裁判例49-1,49-2)などがみられる.一方,いつでも医療施設にアクセスできる社会インフラが整備された現代においては,医師法のなかに応招義務の規定があること自体が時代錯誤であるとして,応招義務不要論を唱える見解3)も近時みられる.
2000年代に入ってから,モンスター・ペイシェントなどと呼ばれる迷惑患者の存在が指摘されるようになり,医療現場が疲弊する原因ともいわれているが,多くの医療者は応招義務の観点から患者の診療を拒否することは困難と考える傾向にあるように思われる.
しかしながら,医師法19条1項の文言から明らかなとおり,「正当な事由」があれば診療を拒むことは可能なのであって,問題はどのような場合に「正当な事由」ありと言えるのかである.
II.「正当な事由」の解釈
過去の裁判例では,医師法19条1項における「正当な事由」について,「原則として医師の不在または病気等により事実上診療が不可能である場合を指す」とするものがあるが(後掲判例12),必ずしも現在における社会情勢に適合しないようにも思われる.
その他には「信頼関係が失われたときは,患者の診療・治療に緊急性がなく,代替する医療機関が存在する場合に限り,医師または医療機関がこれを拒絶しても,診療拒絶に正当事由があると解するのが相当」として,信頼関係の喪失に言及する裁判例(後掲裁判例29-1)もみられる.行政通知においては,令和元年12月25日に厚生労働省医政局から「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」と題する通知4)により,それまでの行政解釈が整理されるに至っているところ,そこでは患者の迷惑行為に関する診療拒否について,「診療・療養等において生じたまたは生じている迷惑行為の態様に照らし,診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には,新たな診療を行わないことが正当化される.」と規定されており,やはり信頼関係の喪失が判断要素とされている.
もっとも,いかなる場合に信頼関係が喪失したと認めることができるのかについては,さらに個々の裁判例を踏まえた具体的検討が必要である.
III.裁判例の分析
応招義務に関するいくつかの主要な裁判例や行政解釈を踏まえて,「正当な事由」の判断基準を検討した報告は過去にもみられた5)6).
筆者らは以前,さらに多くの裁判例を踏まえて,いわば帰納法的に診療拒否に関する裁判例の傾向を明らかにするため,複数の裁判例検索システムを利用して「応招義務」「診療拒否」などの文言を含む裁判例のべ526件を抽出し,さらにデータベースに収載されていない7件も加えた上,医療者が患者に対する診療を行わなかったことについて裁判所の判断が示された昭和3年から令和元年までの50事例,55裁判例(同一事例の上訴審判決を含む)について分析を行った結果を報告した7).その後も診療拒否に関する裁判例が出されているため,今般改めて前回と同条件にて裁判例検索を行った結果,新たに9件の裁判例が抽出されたので,これらを加えた結果を示す(表1).
計64裁判例中,刑事裁判は5件で,うち4件が有罪,1件が無罪であった.医師の応招義務は,明治13年の旧刑法で規定されたときから昭和17年の国民医療法に至るまで罰則付きの規定として存在してきたが,昭和23年に施行された現行医師法においては罰則規定が設けられていないため,昭和13年の裁判例5より後は民事裁判例のみが存在する.
民事裁判例は59件で,うち応招義務違反や医療者の行為の違法性が認められた裁判例が7件,応招義務違反等は認められないと判断された裁判例が52件であった.約88%の裁判例では応招義務違反等はないと判断されていることになる.
以前に分析を行った時点では,平成17年9月8日の最高裁判決で患者の要望する治療を断ったことに関する医療機関側の賠償責任が認められたのを最後に,それ以降は医療者の診療拒否について違法と認められた裁判例はみられなかったが,今回の調査では令和2年の裁判例54と令和3年の裁判例58において医療機関側の賠償責任が認められている.裁判例54は,歯科矯正治療を受けていた患者がHIVに感染したため,そのことを理由に歯科医師が治療を拒絶したことにつき「正当な理由」がないとしたものであり,医療現場の参考となるものと思われる(裁判例58については後述).
類型別の集計では,患者あるいはその家族の迷惑行為や,患者側と医療者との信頼関係の喪失を理由とした診療拒否が問題とされた類型が22件と最も多く,次いで多かったのが,診療拒否という事実自体が認められないとして患者側の主張が排斥された類型の14件であった(表2).
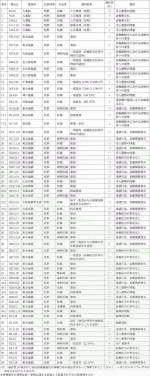
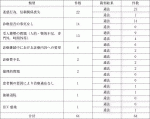
IV.迷惑行為・信頼関係喪失類型の各裁判例
患者側の迷惑行為や医療者と患者との間の信頼関係喪失を理由とした診療拒否に関する各裁判例の概要を示す(表3).
22裁判例中,診療拒否に正当事由がないとされたのは裁判例58の1件のみであり,他の裁判例では全て医療機関側の主張が認められている.裁判例58は,患者による迷惑行為があったと認めるに足る客観的な根拠がないにもかかわらず診療拒否がなされたものであることからすると,患者自身による迷惑行為が客観的に確認された事例では全件において医療機関側の主張が認められているということができる.医療機関側の受入態勢の問題から診療を断ったという類型などに比べ,迷惑行為や信頼関係喪失を理由とした診療拒否については医療機関側の主張が認められやすい傾向にあるといえそうである.
事案の内容をみると,患者の暴言・暴力,いわゆるストーカー行為,業務妨害的行為があった事案においては,警察沙汰になった事案(裁判例19,26,30,35,38,44,51)はもちろんのこと,そうでない事案(裁判例18,31,46)においても,診療拒否に関する医療機関側の責任が否定されている.患者の言動が必ずしも犯罪を構成するようなものではない場合でも,経過等に照らして診療を拒否する正当な事由となり得ることがわかる.
また,明らかな暴言・暴力などがなくとも,患者の苦情内容等に照らして,医療者との信頼関係は失われていたと判断された場合にも,医療機関側の責任が否定されている(裁判例16,37,41).
通院中の医療機関に対し法的手段で責任追及したり,その前段階としての証拠保全を裁判所に申し立てたような事案では,そのような経過も信頼関係喪失の一事情として扱われている(裁判例27,29).もとより,法的手段にて責任追及することは何人にも認められた権利であるため,そのことのみをもって診療拒否が正当化されるものとはいえないが,責任追及の具体的方法・内容の如何によっては,診療拒否に正当事由ありとの判断を根拠づける一事情となり得る.
裁判例21は,特に患者の暴言・暴力や業務妨害行為,法的責任追及などがなされたものではなく,患者が確たる根拠もなく診療費半額の返還請求をしてきたことに対し,以後の受診を断った事案であるが,診療拒否の違法性は否定されている.この事案では,歯科医師が必要として勧める治療を患者が拒否したほか,初診時には診療費が支払われなかったことなどの事情も考慮されたものと推察される.
裁判例24では,過去に支払基金から減点査定を受けたことのある薬剤の処方を医師に求める患者家族と,これを拒む医師との間で口論になり,医師が一方的に以後の診療を拒絶する旨を通告したという事案であるが,診療拒否を理由とした患者の賠償請求は退けられている.また,裁判例25は,患者が診療予約を無断でキャンセルするなどしたほか,当初の契約内容にない治療方法を求めてきたなどの経過を考慮し,やはり患者側の主張が排斥されている.両裁判例とも,暴言・暴力などに関する他の裁判例に比べる限り,患者の言動が問題とされる程度は必ずしも高くないと思われる.迷惑行為ないし信頼関係喪失の類型において,応招義務に関する「正当の事由」の司法判断は,医療現場で通常考えられているところよりも緩やかになされているといえるのではなかろうか.
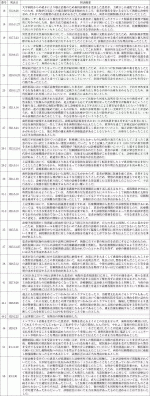
V.違法な診療拒否による賠償額
診療拒否を理由として医療機関が敗訴した民事裁判における認容額についてみると,診療拒否と患者の死亡結果との因果関係を認めた裁判例12と裁判例13において高額の賠償が命じられているが,裁判例15では患者が予後不良の疾患であったことなどから比較的低額の認容額にとどまっている.
患者の死亡結果とは無関係に,医師の診療拒否自体による賠償額が争われた裁判例14では,患者が求めた診療を拒否されることがなく診察を受け得るとの法的利益が侵害されたとして150万円が認容されているが,人的態勢不足を理由に救急患者の受入を断った結果として患者が死亡するに至ったという個別事例に対する評価であり,診療拒否による患者側の損害額として一般化することは困難である.
診療拒否の後に患者に新たな身体障害等が発生していない場合における損害額について判断が示されたものとしては,HIV感染を理由に診療を拒否されたことについて20万円の慰謝料と2万円の弁護士費用の計22万円を認めた裁判例54と,病院関係者に対する第三者の迷惑行為について確たる根拠なく患者の関与によるものと判断して診療拒否を行ったことにつき,同じく20万円の慰謝料と2万円の弁護士費用の計22万円を認めた裁判例58がある.もとより個別事例に対する判断ではあるものの,診療拒否それ自体による精神的損害額を示すものとして参考になるであろう.
VI.おわりに
患者の迷惑行為を原因として診療拒否がなされた裁判例について分析した結果,患者による迷惑行為が客観的に確認されている事例では,全件において医療機関側の主張が認められている.各裁判例の内容をみても,必ずしもモンスター・ペイシェントと呼ばれるような著しい迷惑行為を行う患者に関するものばかりでもなく,応招義務における「正当な事由」については緩やかに認定されていると思われるものも存在する.
また,診療拒否が違法とされた事例についても,その後に新たな身体障害等が発生していない限り,診療拒否それ自体による慰謝料認定額は比較的低額にとどまっている.
医療者としては応招義務の規定の存在自体は認識しているために,基本的に診療拒否はできないとの先入観のもと,対応困難事例においても患者の求めに応じて診療を行わざるを得ないこともあったかもしれない.
限られた人的・物的医療資源を適切に運用して安全で質の高い医療を安定的に提供していくためにも,特に患者の迷惑行為などには毅然と対応し,ときには院外の専門家などとも協調するなどして,適切な手続きを踏んだ上で診療拒否を行うことも検討されてよいのではないだろうか.
利益相反:なし
文献
1) 美濃部 達吉:行政上より見たる醫師不應招問題(一).法律新聞,1047:5,1915.
2) 池田 清志:改正醫師歯科醫師法令釋義,日本醫事衛生通信社,pp290-302,1933.
3) 畔柳 達雄:医師の応招義務,日本医師会ホームページ.2020年8月4日. https://www.med.or.jp/doctor/member/kiso/d30.html
4) 令和元年12月25日厚生労働省医政局長通知:医政発1225第4号.
5) 水沼 直樹:応招義務の歴史的展開と診療拒絶の可否.医療判例解説,56:1-6,2015.
6) 三谷 和歌子,吉峯 耕平,大寺 正史:応招義務と「正当な事由」の判断基準の類型的検討.日医師会誌,145:1655-1659,2016.
7) 棚瀬 慎治,内藤 俊夫,小林 弘幸:診療拒否に関する裁判例の分析.日病総合診療医会誌,17:157-163,2021.
PDFを閲覧するためには Adobe Reader が必要です。